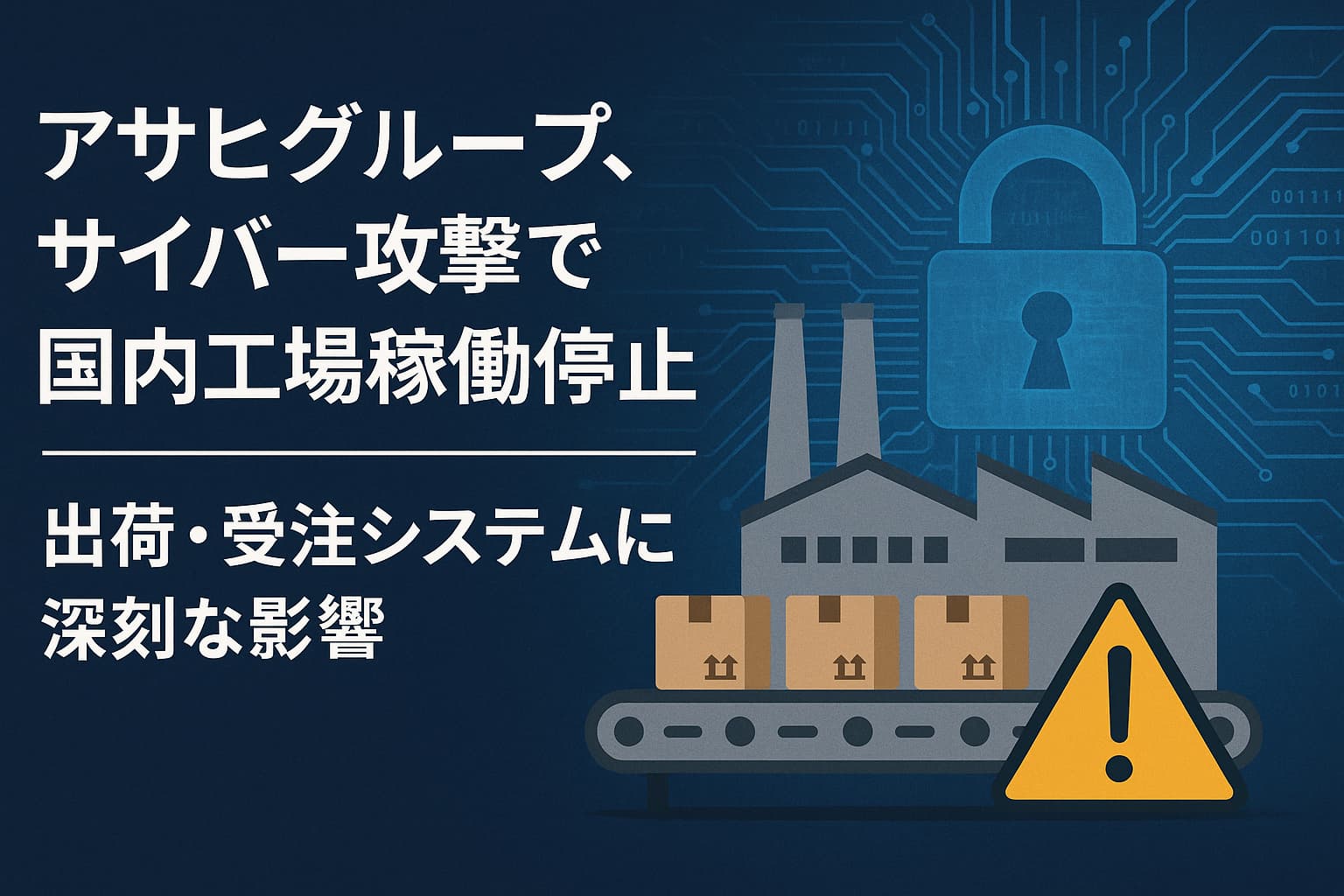はじめに
2025年9月29日、アサヒグループホールディングスは、グループの国内システムがサイバー攻撃を受け、業務システム全般に障害が発生したことを公表しました。これにより、国内の複数工場での生産が停止し、受注や出荷業務、さらにコールセンターによる顧客対応までもが機能しない状態に陥っています。
近年、製造業を狙ったサイバー攻撃は世界的に増加しており、事業継続性やサプライチェーン全体への影響が懸念されています。アサヒグループは日本を代表する飲料・食品企業であり、その規模や社会的影響力を考えると、今回の攻撃は単なる一企業のトラブルにとどまらず、流通網や消費者生活にも広がり得る重大な事案です。
本記事では、現時点で公表されている情報を整理し、事案の概要、影響範囲、そして不明点や今後の注視点について事実ベースでまとめます。
事案の概要
2025年9月29日、アサヒグループホールディングス(以下、アサヒ)は、グループの国内システムがサイバー攻撃を受けたことにより、業務に深刻な障害が発生していると発表しました。発表は公式サイトおよび報道機関を通じて行われ、同社の国内事業全般に及ぶ影響が確認されています。
まず影響を受けたのは、受注システムと出荷システムです。これにより、販売店や取引先からの注文を受け付けることができず、倉庫・物流システムとも連携できない状況となっています。また、工場の生産ラインも一部停止しており、原材料投入から製品出荷に至る一連のサイクルが寸断された形です。日本国内に30拠点以上ある製造施設の一部が直接的に停止していると報じられています。
さらに、顧客対応にも大きな支障が生じています。通常であれば消費者や取引先からの問い合わせを受け付けるコールセンターや「お客様相談室」が稼働停止状態にあり、消費者サービスの面でも機能が途絶しています。現場の従業員もシステム障害により業務が滞っているとみられ、販売網や流通部門を含む広範囲に影響が拡大しているのが現状です。
一方で、アサヒは現時点で個人情報や顧客情報の流出は確認されていないと強調しています。ただし、調査は継続中であり、今後新たな事実が判明する可能性は排除できません。攻撃手法や侵入経路についても具体的な公表はなく、ランサムウェアを含む攻撃であるかどうかも現段階では不明です。
復旧の見通しについては「未定」とされ、いつ通常稼働に戻れるかは全く明らかになっていません。飲料・食品業界は季節要因により需要変動が大きい業種であり、在庫や流通の停滞が長期化した場合、市場全体や取引先企業への波及が懸念されています。
影響範囲
今回のサイバー攻撃によって影響を受けた範囲は、単なるシステム障害にとどまらず、事業運営の根幹に広がっています。現時点で判明している影響を整理すると、以下のように分類できます。
1. 国内事業への影響
- 受注・出荷業務の停止 販売店や流通業者からの注文をシステム上で処理できない状態となり、倉庫・物流システムとの連携も途絶しています。これにより、流通網全体に遅延や停止が発生しています。
- 工場の稼働停止 国内複数の工場において生産ラインが停止。原材料の投入から製品の完成・出荷に至るサイクルが中断し、出荷予定に大きな支障をきたしています。飲料・食品業界は需要の季節変動が大きいため、タイミング次第では市場への供給不足を招く懸念もあります。
- 顧客対応の中断 コールセンターや「お客様相談室」といった顧客窓口が稼働できず、消費者や取引先からの問い合わせに応答できない状況です。企業イメージや顧客満足度に対する悪影響も避けられません。
2. 海外事業への影響
- 現時点の発表および報道によれば、海外拠点の事業には影響は及んでいないとされています。国内と海外でシステム基盤が分離されている可能性があり、影響範囲は日本国内に限定されているようです。
- ただし、海外展開における原材料供給や物流網を国内に依存しているケースもあるため、国内障害が長期化すれば海外事業にも間接的な影響が波及する可能性があります。
3. サプライチェーンへの波及
- サイバー攻撃によるシステム停止は、アサヒ単体にとどまらず、原材料供給業者や物流業者、販売店など広範なサプライチェーンに影響を及ぼすリスクを孕んでいます。
- 特にビールや飲料は流通在庫の消費スピードが速く、出荷遅延が短期間で小売店や飲食業界に波及する可能性があります。これにより、販売機会の損失や顧客離れといった二次的被害が発生する恐れがあります。
4. 社会的影響
- アサヒは日本を代表する飲料・食品メーカーであり、今回の障害は消費者の生活や取引先企業の業務に直結します。特に年末商戦や大型イベントシーズンを控えた時期であれば、市場に与える影響は一層大きくなると予想されます。
不明点と今後の注視点
今回の事案は、公式発表や報道で確認できる情報が限られており、多くの点が依然として不透明なままです。これらの不明点を整理するとともに、今後注視すべき観点を以下に示します。
1. 攻撃手法と侵入経路
- 現時点では、攻撃がどのような手段で行われたのか明らかにされていません。
- ランサムウェアのようにシステムを暗号化して身代金を要求するタイプなのか、あるいは標的型攻撃による情報窃取が目的なのかは不明です。
- 社内システムへの侵入経路(VPN、メール添付、ゼロデイ脆弱性の悪用など)も特定されておらず、同業他社や社会全体に対する再発防止策の検討には今後の情報開示が不可欠です。
2. 情報流出の有無
- アサヒ側は「現時点で個人情報や顧客情報の流出は確認されていない」としていますが、調査が継続中である以上、将来的に流出が判明する可能性を排除できません。
- 特に取引先情報や販売網のデータは広範囲に及ぶため、仮に流出すれば二次被害が発生する懸念があります。
3. 被害規模と復旧見通し
- 受注・出荷・工場稼働が停止しているものの、具体的にどの拠点・どの業務まで影響が及んでいるかは公表されていません。
- 復旧に必要な期間についても「未定」とされており、短期間で回復できるのか、数週間以上にわたる長期障害となるのかは不透明です。
- 復旧プロセスにおいてシステムの再構築やセキュリティ強化が必要になれば、業務再開まで時間がかかる可能性もあります。
4. 外部機関の関与
- 今後、警察や情報セキュリティ当局が関与する可能性があります。
- 経済産業省やIPA(情報処理推進機構)へのインシデント報告が行われるかどうか、またそれに伴う調査結果が公開されるかどうかは注視すべき点です。
5. サプライチェーンや市場への影響
- 出荷停止が長引けば、小売店や飲食業界に供給不足が生じる可能性があります。
- 他の飲料メーカーへの発注シフトなど、競合各社や市場全体への波及効果も今後の焦点となります。
- 海外事業への直接的な影響はないとされていますが、国内障害が長期化すれば間接的に海外展開へ波及するリスクも否定できません。
6. 信用・法的リスク
- 顧客や取引先からのクレーム対応、契約違反に基づく損害賠償リスク、株価下落による企業価値への影響など、二次的な影響も懸念されます。
- 今後の調査で情報流出が確認された場合には、個人情報保護法に基づく公表義務や行政処分の可能性もあり、法的リスクの有無も注目点です。
おわりに
今回のアサヒグループに対するサイバー攻撃は、単なる情報漏洩リスクにとどまらず、国内工場の稼働停止や受注・出荷の中断といった事業継続そのものに直結する重大な影響をもたらしました。特に飲料・食品といった生活に密着した分野で発生したことから、消費者や取引先に及ぶ影響は計り知れず、今後の復旧状況が大きく注目されます。
近年、製造業を狙ったサイバー攻撃は増加傾向にあり、単なる個人情報や顧客データの流出にとどまらず、工場の稼働停止やサプライチェーン全体の混乱を引き起こす事例が目立っています。先日報じられたジャガーの事案においても、システム障害が生産ラインの停止に直結し、企業活動そのものが制約を受ける深刻な影響が示されました。これらの事例は、サイバー攻撃が企業にとって「情報セキュリティ上の問題」だけではなく、「経営・オペレーション上のリスク」として捉える必要があることを改めて浮き彫りにしています。
今回のアサヒグループのケースも同様に、被害の全容解明や復旧の見通しが未だ不透明な中で、製造業や社会インフラを支える企業にとっては、システムの多重防御や事業継続計画(BCP)、さらにはサイバー攻撃を前提としたリスク管理体制の強化が急務であることを示すものです。個人情報の漏洩に注目が集まりがちですが、それ以上に重要なのは、工場の操業停止や物流の麻痺といった現実的かつ直接的な被害に備えることです。
本件は、日本の製造業全体にとって警鐘であり、各社が自社のセキュリティ体制と事業継続戦略を再点検する契機となるべき事案といえるでしょう。
参考文献
- Japan’s beer giant Asahi Group cannot resume production after cyberattack
https://www.reuters.com/technology/japans-beer-giant-asahi-group-cannot-resume-production-after-cyberattack-2025-09-30/ - サイバー攻撃によるシステム障害発生について
https://www.asahigroup-holdings.com/newsroom/detail/20250929-0102.html - アアサヒグループHD、サイバー攻撃によるシステム障害発生を発表
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/2051098.html - サイバー攻撃でシステム障害、調査や復旧急ぐ – アサヒグループHD
https://www.security-next.com/175046 - アサヒグループHDがサイバー攻撃でシステム障害続く 国内の飲料・食品の受注や出荷ストップ 復旧メド立たず
https://www.fnn.jp/articles/-/938467 - アサヒビール、サイバー攻撃で受注・出荷停止――ランサムウェアが狙う日本企業
https://innovatopia.jp/cyber-security/cyber-security-news/67511/