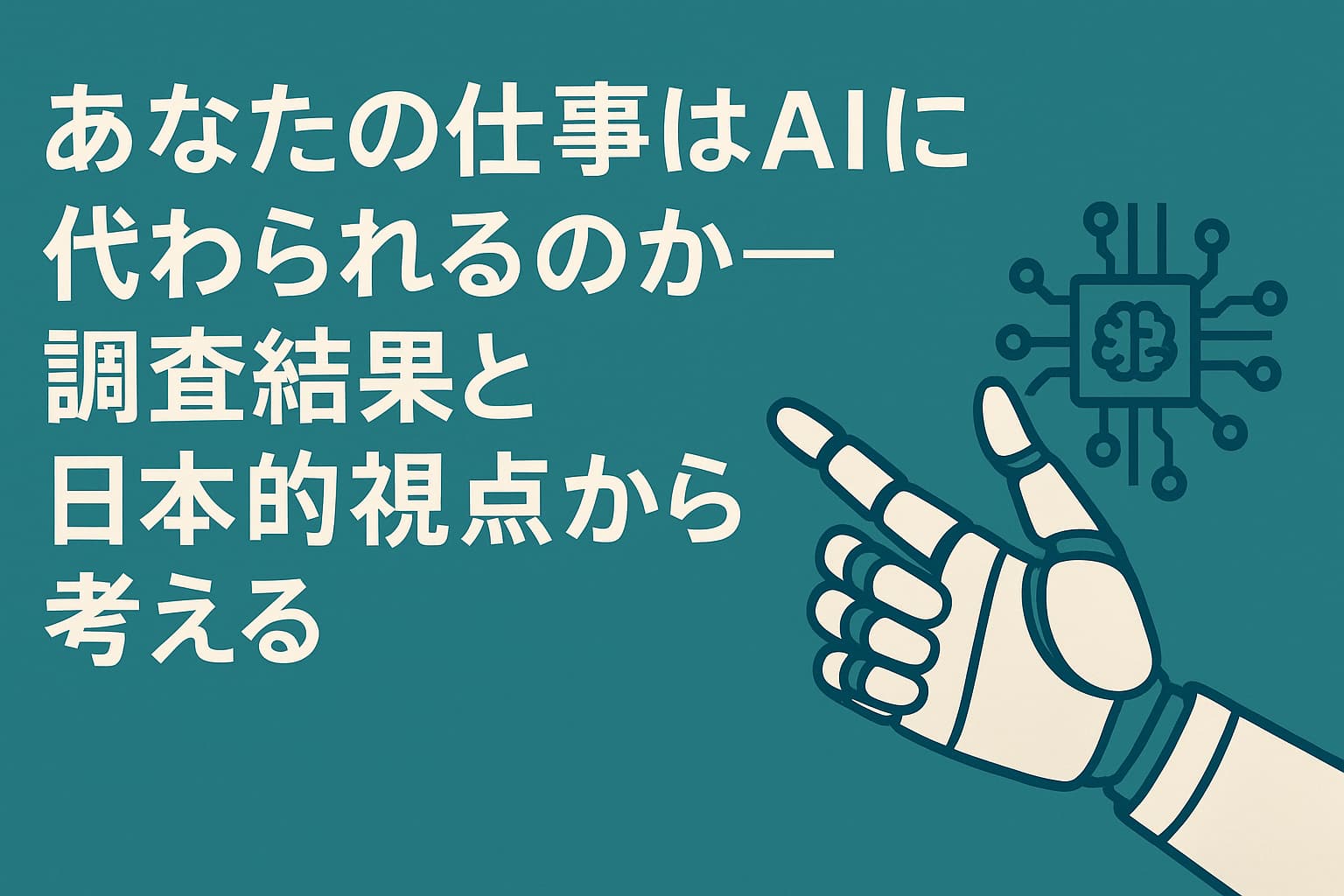― Microsoft ResearchのCopilot会話データから読み解く ―
2025年7月、Microsoft Researchが発表した論文「Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI」は、生成AIがどの職業にどれほど影響を与えるかを定量的に分析したものです。
非常に読み応えのある研究ですが、私たちはこの結果を“そのまま”信じるべきではありません。なぜなら、そこには文化的前提・技術的制限・そして人間らしさの視点の欠如があるからです。この記事では、この研究内容を簡潔に紹介しつつ、AIとどう向き合っていくべきかを考えていきます。
📊 論文の概要──AIが“できること”で職業をスコア化
本論文は、AIが実際に人々の仕事の中でどのように使われているのかを、「現場の利用データ」から明らかにしようとする非常に実践的な研究です。対象となったのは、2024年1月から9月までの9か月間における、Microsoft Bing Copilot(現在のMicrosoft Copilot)とユーザーとの20万件の会話データです。
このデータには個人を特定できる情報は含まれておらず、すべて匿名化されていますが、会話の内容から「どんな作業のためにAIが使われたのか」「AIがどのような役割を果たしたのか」が把握できるようになっています。
著者らはこれらの会話を次の2つの視点から分析しています:
- User Goal(ユーザーの目的):ユーザーがAIに依頼した作業内容。 例:情報収集、文章作成、技術的なトラブル対応など。
- AI Action(AIが実際に行った行動):AIが会話の中で実際に果たした役割。 例:説明、助言、提案、文書生成など。
これらのやり取りを、アメリカ労働省が提供する詳細な職業データベース O*NET の中に定義された「中間的業務活動(IWA)」に分類し、それぞれの業務に対するAIの関与度を測定しています。
さらに、単に「その業務が登場したかどうか」だけでなく、
- その会話がどれくらいうまく完了したか(タスク成功率)
- AIがその業務のどの程度の範囲をカバーできたか(影響スコープ)
- その業務が職業全体の中でどれくらいの比重を占めているか(業務の重要度)
といった要素を総合的に加味し、各職業ごとに「AIの適用性スコア(AI Applicability Score)」を数値化しています。
このスコアが高ければ高いほど、その職業はAIによって大部分の業務を代替・支援できる可能性が高いということを示します。逆にスコアが低ければ、AIによる代替は難しい、あるいは業務の性質がAI向きでないと判断されます。
重要なのは、このスコアが「AIが“できること”の積み上げ」で構成されており、実際の業務現場でAIが何を担っているかというリアルな利用実態に基づいているという点です。
つまり、これは理論や想像ではなく、「今この瞬間、ユーザーがAIに何を任せているのか」の集合体であり、非常に具体的で現実的な分析であることが、この研究の価値とユニークさを形作っています。
📈 AIに置き換えられやすい職業(上位)
MicrosoftとOpenAIの研究チームが2024年に発表した本論文では、生成AI(特にBing Copilot)の使用実態をもとに、AIが補助・代替可能な職業をスコア化しています。
スコアが高いほど、現実的に生成AIに置き換えられる可能性が高いとされます。その結果、意外にも多くのホワイトカラー職・知的労働が上位にランクインすることになりました。
🏆 生成AIに置き換えられやすい職業・上位10位
| 順位 | 職業名 | 主な理由・特徴 |
|---|---|---|
| 1 | 翻訳者・通訳者 | 言語処理に特化したLLMの進化により、多言語変換が自動化可能に |
| 2 | 歴史家 | 膨大な情報の要約・整理・分析が生成AIに適している |
| 3 | 客室乗務員(Passenger Attendants) | 安全説明や案内など定型的な言語タスクが多く、自動化しやすい |
| 4 | 営業担当者(Sales Reps) | 商品説明やQ&AがAIチャットやプレゼン生成で代替可能 |
| 5 | ライター・著者(Writers) | 構成、草案、文章生成の自動化が進み、創作の一部がAIでも可能に |
| 6 | カスタマーサポート担当 | FAQや定型応答は生成AIチャットボットが得意とする領域 |
| 7 | CNCツールプログラマー | コードのテンプレート化が可能で、AIによる支援の精度も高い |
| 8 | 電話オペレーター | 一方向の定型的応対は自動応答システムに置き換えられる |
| 9 | チケット・旅行窓口職員 | 日程案内・予約対応など、AIアシスタントが即時対応可能 |
| 10 | 放送アナウンサー・DJ | 原稿の読み上げや構成作成をAIが行い、音声合成で代替されつつある |
🔍 傾向分析:身体よりも「頭を使う仕事」からAIの影響を受けている
このランキングが示しているのは、「AIに奪われるのは単純作業ではなく、構造化可能な知的業務である」という新しい現実です。
特に共通するのは以下の3点です:
- 言語・情報を扱うホワイトカラー職
- データ処理や文書作成、問い合わせ対応など、テキストベースの業務に生成AIが深く入り込んでいます。
- 定型化・マニュアル化された業務
- パターンが明確な業務は、精度の高いLLMが得意とする領域。反復作業ほど置き換えやすい。
- 「感情のやり取り」が少ない対人職
- 客室乗務員や窓口業務なども、説明・案内中心であれば自動化しやすい一方、「思いやり」や「空気を読む力」が求められる日本型サービス業とは前提が異なります。
🤖 翻訳者が1位に挙がったことへの違和感と現場のリアル
特に注目すべきは「翻訳者・通訳者」が1位である点です。
確かにAIによる翻訳精度は日進月歩で進化しており、基本的な文章やニュース記事の翻訳はもはや人間が介在しなくても成立する場面が増えてきました。
しかし、日本の翻訳業界では次のような現場視点からの議論が活発に交わされています:
- 映画の字幕、文学作品、広告文などは文化的背景や語感、ニュアンスの調整が必要で、人間の意訳力が不可欠
- 外交通訳や商談通訳では、「あえて曖昧に訳す」などの配慮が要求され、LLMには困難
- 翻訳者は「AIの下訳」を編集・監修する役割として進化しつつある
つまり、「翻訳」は単なる変換作業ではなく、その文化で自然に響く言葉を選び直す“創造的な営み”でもあるということです。
したがって「代替」ではなく「協業」に進む道がすでに見えています。
⚖️ AIに任せるべきこと・人がやるべきこと
このランキングは「すぐに職がなくなる」という意味ではありません。
むしろ、業務の中でAIが代替できる部分と、人間にしかできない創造的・感情的な価値を分ける段階に来たといえます。
💡 働く人にとって大切なのは「自分にしか出せない価値」
仕事に従事する側として重要なのは、「誰がやっても同じこと」ではなく、「自分だからこそできること」を強みに変える姿勢です。
- 翻訳なら、読み手に響く言葉選び
- 営業なら、顧客ごとの温度感を読むセンス
- 文章作成なら、構成や視点のユニークさ
こうした「個性」「文脈把握力」「信頼形成」は、現時点でAIには困難な領域であり、これこそが人間の競争力となります。
🎯 結論:AIは“同じことをうまくこなす”、人は“違うことを価値に変える”
この研究は「AIが職を奪う」ものではなく、「どんな職でもAIが補助役になる時代が来る」という前提で読むべきものです。
AIに脅かされるのではなく、AIを使いこなして“人間にしかできない価値”をどう磨くかが、これからのキャリア形成の鍵になります。
📉 AIに置き換えにくい職業(上位)
生成AIの進化は目覚ましく、あらゆる業務の自動化が議論されていますが、依然として「AIでは代替できない」とされる職業も多く存在します。論文では、AIによる代替可能性が低い職業をスコアリングし、人間であること自体が価値になる職業を明らかにしています。
🏅 生成AIに置き換えにくい職業・上位10位
| 順位 | 職業名 | 主な理由・特徴 |
|---|---|---|
| 1 | 助産師(Midwives) | 高度な身体介助+強い信頼関係と心理的ケアが不可欠 |
| 2 | 鉄筋工(Reinforcing Ironworkers) | 精密な手作業と臨機応変な現場判断が要求される |
| 3 | 舞台関係技術者(Stage Technicians) | アナログ機材の扱いや即応性、チーム連携が鍵 |
| 4 | コンクリート仕上げ作業員 | 感覚に頼る現場作業。職人技術が不可欠 |
| 5 | 配管工(Plumbers) | 複雑な構造・現場環境に応じた柔軟な施工判断が必要 |
| 6 | 幼児教育者(Preschool Teachers) | 子どもの成長に寄り添う繊細な感受性と柔軟な対応力 |
| 7 | 屋根職人(Roofers) | 危険な高所作業と現場ごとの調整が求められる |
| 8 | 電気工(Electricians) | 安全管理と即時判断、手作業の両立が必要 |
| 9 | 料理人・調理師(Cooks) | 感覚と創造性が問われる“手仕事”の極み |
| 10 | セラピスト(Therapists) | 心のケアは人間にしか担えない領域 |
🔍 傾向:身体性・即応性・人間関係がカギ
上位に並ぶ職業には共通の特徴があります:
- 現場での経験と判断が必要(電気工・配管工など)
- 身体を使って手を動かすことが前提(鉄筋工・調理師など)
- 感情や信頼を介した対人関係が重要(助産師・幼児教育者・セラピスト)
これらはAIが最も不得意とする領域であり、マニュアル化できない臨機応変さや空気を読む力が問われる仕事です。
💬 セラピストは「置き換えにくい」のではなく「置き換えてはならない」
特に注目すべきは、10位にランクインしているセラピストです。
生成AIは、自然な対話や感情分析が可能になりつつありますが、セラピーの現場では単なる対話以上のものが求められます。
❗ AIとの会話によって悪化するケースも
近年、AIとの会話で孤独感や抑うつが深まったという報告が出ています。
- 感情を正確に理解しないAIが返す「合理的すぎる言葉」によって傷つく人
- “共感”が上滑りすることで、「話をしても伝わらない」という深い虚無感
- 長時間のAIとの対話が、かえって人間との対話のハードルを上げてしまう
など、精神的に不安定な状態でのAI活用にはリスクがあることが指摘されています。
🤝 セラピーには「関係性」が必要不可欠
セラピストの本質は、問題解決ではなく「人として寄り添うこと」にあります。
表情、沈黙、呼吸、雰囲気──言葉にならないものすべてを含めて理解し、受け止める力が必要とされます。
これは、現時点のAI技術では模倣すら困難であり、倫理的にもAIに担わせるべきではない分野です。
✅ AIは補助的には活用できる
AIが果たせる役割としては以下のようなものが考えられます:
- 日々の感情の記録・傾向の可視化
- 初期段階の相談や予備的カウンセリングのサポート
- セラピストによる判断のための補助的分析
つまり、AIは「主役」ではなくセラピーの下支えとなる道具であるべきなのです。
🇯🇵 日本文化における“人間らしさ”の重視
日本では、「おもてなし」や「察する文化」が根付いており、人と人との関わりに強い意味を持たせる傾向があります。
そのため、以下のような職業は特にAIによる置き換えが難しいと考えられます。
- セラピスト・カウンセラー:感情の間合いを読む力が本質
- 保育・介護:身体的な寄り添いと、信頼関係の構築
- 飲食・接客:言葉にしない“気遣い”の文化
米国のように「効率化された対人サービス」が存在する国ではAIへの代替が進むかもしれませんが、日本社会では人間同士の温度感こそがサービスの質であり、AIでは再現できない文化的価値があるのです。
✅ 結論:「置き換えにくい職業」は、むしろ“人間らしさ”の価値を再定義する
AI時代において、「人間にしかできない仕事」は単に技術的に難しいからではありません。それが人間にしか担えない“責任”や“配慮”で成り立っているからこそ、AIには譲れないのです。セラピストはその象徴であり、「心を扱うことの重み」と「人と人との関係性の尊さ」を再認識させてくれる存在です。今後は、AIとの共存を模索しつつも、“人が人である価値”を守る職業の重要性がますます高まっていくでしょう。
🤖「知識労働=安全」は幻想? 作業が分解されればAIの対象に
かつては「肉体労働はAIやロボティクスに代替されるが、知識労働は安全」と言われてきました。
しかし、この論文が示すように、その前提はすでに揺らぎ始めています。
本研究では、各職業の「タスクレベルのAI対応可能性」に注目しています。つまり、職業そのものではなく、業務を構成する作業単位(タスク)をAIがどこまで担えるかをスコアリングしているのです。
🔍 重要なのは「職業」ではなく「作業の分解」
例えば「データサイエンティスト」や「翻訳者」といった職種は高度なスキルが必要とされますが、次のような構造を持っています。
- 📊 データのクレンジング
- 🧮 モデルの選定と実装
- 📝 レポートの作成と可視化
これらの中には、すでにAIが得意とするタスクが多数含まれており、職種全体ではなく一部の作業がAIに吸収されることで、業務全体が再編されていくのです。
翻訳や通訳も同様です。文法的な翻訳はAIで高精度に実現できますが、文化的・情緒的なニュアンスを含む意訳、機微を伝える翻訳、外交交渉の通訳などは人間の経験と判断に基づく知的作業です。しかし、それ以外の定型的なタスクが自動化されれば、「1人の翻訳者が抱える業務量の再分配」が起こるのは避けられません。
⚙️ 作業が標準化・形式化されるほどAIに置き換えられやすい
本研究が示している本質は次の通りです:
「知識労働であっても、定型的で再現可能なタスクに分解できるならば、AIによって置き換えられる」
これは極めて重要な観点です。
- 「専門性があるから安全」ではなく、
- 「再現可能な形式に落とし込まれたかどうか」が鍵になります。
つまり、かつては職種ごとに「これはAIでは無理だろう」と語られていたものが、GPTのような言語モデルの登場によって、一気に処理可能領域へと押し広げられたという現実があります。
たとえば:
| 職業カテゴリ | 対象とされる作業 | AIに置き換えやすい理由 |
|---|---|---|
| データサイエンティスト | 前処理・EDA・定型レポートの生成 | ルール化・テンプレート化が可能 |
| 法務アシスタント | 契約書レビュー・リスクチェック | 過去データに基づくパターン認識が可能 |
| 翻訳者・通訳者 | 文書翻訳・逐語通訳 | 文脈処理と文章生成はLLMが得意 |
| カスタマーサポート | 定型問い合わせ対応 | チャットボット化が容易、24時間対応可能 |
🧩 結論:知識労働であっても、差別化されない作業はAIに代替される
論文で示されたランキングは、単に職業名だけを見て「この仕事は危ない」と断じるためのものではありません。むしろ、その職業がどういった作業に支えられ、何が自動化され得るかを見極めるための出発点です。
知識労働であっても、「誰がやっても同じ結果になる作業」は真っ先にAIに置き換えられます。
その一方で、人間ならではの判断・感性・解釈が求められる部分にこそ、今後の価値が残っていくことになります。
したがって、私たちは職業の肩書きに安住するのではなく、「自分の中でしか発揮できない強み」や「解釈・表現の個性」を常に研ぎ澄ます必要があるのです。
🧠 協業と差別化の時代──“あなたでなければならない”価値を
AIが一部の業務を担い始めた今、私たちは仕事を「奪われるかどうか」ではなく、どうやってAIと協業していくかを考える段階に入っています。
前述のように、多くの仕事がAIによって“分解”可能になったことで、業務の一部が置き換えられるケースが増えてきました。しかしそれは裏を返せば、人間にしかできない部分がより明確になってきたということでもあります。
🔍 AIができること vs あなたにしかできないこと
AIは「知識」や「情報の再構成」に長けていますが、以下のような領域ではまだまだ人間の方が優位です:
| AIが得意なこと | 人間が得意なこと |
|---|---|
| ルールや文法に基づくタスク処理 | 文脈・感情・空気を読む |
| データの統計処理・分析 | あいまいな状況下での判断 |
| 論理的に一貫した文章の生成 | 微妙なニュアンスや意図の表現 |
| 類似データからの推論 | 創造・アイデアの飛躍的な発想 |
言い換えれば、「誰がやっても同じ」仕事はAIに代替されやすく、逆に「その人だからできる」仕事は今後ますます重要になるのです。
これは、あなたの経験、感性、信頼関係、ストーリーテリング能力など、単なるスキルではなく“個性”が武器になる時代が到来したとも言えるでしょう。
🧭 「差別化」と「協業」が両立する働き方
今後の働き方の理想は、AIがあなたの相棒になることです。
- AIがデータ整理やルーチンタスクを処理し、あなたは創造・判断・対話に集中する
- 提案資料やレポートのドラフトはAIが下書きし、あなたが仕上げる
- 24時間体制のチャットサポートはAIが担い、あなたは難しい対応や対人関係に注力する
このような人間とAIのハイブリッドな働き方が、これからのスタンダードとなるでしょう。
重要なのは、「AIが得意なことは任せて、自分は人間ならではの強みで差別化する」という意識を持つことです。「協業」が前提となる時代では、差別化は自己保身の手段ではなく、価値創出のためのアプローチとなります。
🧑🎨 あなたでなければならない理由を育てる
あなたの仕事において、「なぜ私がこの仕事をしているのか?」という問いを自分に投げかけてみてください。
その答えの中に、
- 他の人にはない経験
- 目の前の人への共感
- 自分なりのやり方や信念
といった、“あなたでなければならない”理由が眠っているはずです。
AIと共に働く社会では、こうした個人の内面や背景、信頼、関係性が、今以上に仕事の価値を決定づけるようになります。
AI時代の働き方とは、AIに勝つのではなく、AIと共に自分の価値を磨くこと。そのために必要なのは、“誰かの代わり”ではなく、“あなただからできる”仕事を見つけ、育てていく視点です。協業と差別化が共存するこの時代に、あなた自身の声・視点・存在そのものが、かけがえのない価値になるのです。
🇯🇵 対人業務は文化によって捉え方が違う──日本の現実
本論文では、米国においてAIに置き換えられやすい職業の上位に「受付」「レセプショニスト」「カスタマーサービス」などの対人業務が含まれているという結果が示されています。
これは一見すると「人と接する仕事はAIでも代替可能」という結論に見えますが、この前提は文化圏によって大きく異なるという点に注意が必要です。
🏬 「人と接すること」への価値観──日米の違い
たとえば、アメリカのスーパーでは、レジ係がガムを噛みながら無言で接客するような、効率最優先のサービス文化が一般的とされるケースもあります。
こうした背景があれば、感情表現を模倣するAIでも一定の接客ニーズを満たせると考えられるのは当然でしょう。
一方、日本では接客業において、
- 丁寧なお辞儀や言葉遣い
- 相手の気持ちを察する応対
- 表には出ないけれど重要な「気配り」や「間合い」
といった、非言語的な配慮や細やかな気遣いが評価される文化があります。
このような「おもてなしの心」は、単なるタスクではなく、文化的なコミュニケーション様式の一部といえます。
🧠 「人間性を求める仕事」は簡単には代替できない
接客や対人対応において、AIはマニュアル通りの対応やテンプレート応答は可能でも、
- 顧客の感情を読み取って臨機応変に対応する
- 微妙な空気感を察して言葉を選ぶ
- 「無言」の時間を不快にしない間合いを取る
といった高度な対人スキルを再現することは、技術的にも倫理的にも難しい段階にあります。
特に日本のように、「察する」「空気を読む」といった高度に文脈依存のコミュニケーション文化においては、AIが本質的に人間と同じようにふるまうのは困難です。
そのため、日本では対人業務のAI化はより限定的かつ慎重に進められるべき領域だといえるでしょう。
🌏 グローバルなAI導入における文化的配慮
このように、「対人業務=AIに代替可能」という単純な図式は、文化的な文脈を無視してしまうと誤った理解を生み出す危険性があります。
- アメリカや欧州では「感情の伝達は合理的であるべき」という考え方が根強く、AIによる最低限の会話で十分と見なされることも多い
- 日本や東アジアでは、コミュニケーションは内容だけでなく「態度」や「空気の和」も重視され、人間らしさそのものがサービスの価値となる
つまり、対人業務がAIに置き換えられるかどうかは「業務内容の合理性」だけでなく、「その国・地域の文化や美意識」に深く関係しているのです。
🇯🇵 日本における「人を介す価値」は、むしろ強まる可能性も
生成AIの普及が進むにつれ、「人間にしかできない仕事とは何か?」がより強く意識されるようになります。
そうした中で日本では、以下のような業務において“人であることの価値”が再評価される可能性があります。
- 高級旅館や料亭での接客
- 医療・介護現場での心のケア
- 学校や職場におけるメンタルサポート
- 面談やカウンセリングのような“傾聴”を重視する仕事
これらは、単なる情報伝達ではなく「人間らしさ」そのものが本質となる職業であり、文化的背景の影響を強く受けています。
🔚 おわりに:あなたの仕事には、あなたらしさがあるか?
AIの進化は、もはや“いつか来る未来”ではなく、“今、目の前にある現実”になりました。
多くの人が、生成AIや自動化ツールを使う日常の中で、「この仕事、本当に人間がやる必要あるのかな?」とふと思ったことがあるかもしれません。
実際、本記事で紹介した研究論文のように、AIが“現実にこなせる仕事”の範囲は、かつてない速度で拡大しています。
しかし、それと同時に問い直されるのが──
「自分の仕事には、他の誰でもなく“自分”がやる意味があるのか?」
という、働く人一人ひとりの存在意義です。
🎨 AIには出せない「あなたの色」
あなたの仕事には、次のような“あなたらしさ”があるでしょうか?
- 提案内容に、あなたの価値観や人生経験がにじみ出ている
- 同じ仕事でも、あなたがやると「なんだか安心する」と言われる
- 期待された以上のことを、自発的に形にしてしまう
- 失敗しても、それを次に活かそうとする強い意思がある
これらはどれも、AIには持ち得ない“個性”や“感情”、そして“関係性”の中で育まれる価値です。
🧑🤝🧑 “こなす”仕事から、“応える”仕事へ
AIは“タスク”を処理しますが、人間の仕事は本来、“相手の期待や状況に応じて応える”ものです。
言われたことだけをやるのではなく、「この人のためにどうするのが一番いいか?」を考え、試行錯誤する──
その中にこそ、あなたが働く意味があり、あなたにしかできない仕事の形があるのではないでしょうか。
🧱 “仕事を守る”のではなく、“自分をアップデートする”
AIの進化は止められませんし、「AIに奪われないように」と恐れても、それは防波堤にはなりません。大切なのは、自分の仕事をどう再定義し、どんな価値を加えられるかを考え続けることです。
- AIと協業するために、どうスキルを変えていくか
- 誰に、何を、どう届けるのかを再設計する
- 「人間にしかできないことは何か?」を問い続ける
それは、職種や業界に関係なく、あらゆる仕事に携わる人が向き合うべき問いです。
🔦 最後に
あなたの仕事は、他の誰でもない「あなた」である意味を持っていますか?
それを意識することが、AI時代においても働くことの価値を見失わない最大の防衛策であり、同時に、AIを“道具”として使いこなし、自分らしい仕事を創造するための出発点になるはずです。AI時代に問い直されるのは、“どんな仕事をするか”ではなく、“どうその仕事に関わるか”です。
だからこそ、今日から問いかけてみてください──
「この仕事、自分らしさを込められているだろうか?」 と。
📚 参考文献
- Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/working-with-ai-measuring-the-occupational-implications-of-generative-ai/ - Generative AI exposure metrics by occupation (arXiv:2507.07935v3)
https://arxiv.org/abs/2507.07935 - Why ChatGPT and AI won’t replace translators and interpreters (Slator)
https://slator.com/why-chatgpt-and-ai-wont-replace-translators-and-interpreters/ - The cultural differences in customer service between Japan and the West (Nippon.com)
https://www.nippon.com/en/features/h00177/ - Therapists Warn of Mental Health Risks from AI Companions (Psychology Today)
https://www.psychologytoday.com/us/blog/artificial-you/202305/therapists-warn-of-mental-health-risks-from-ai-companions