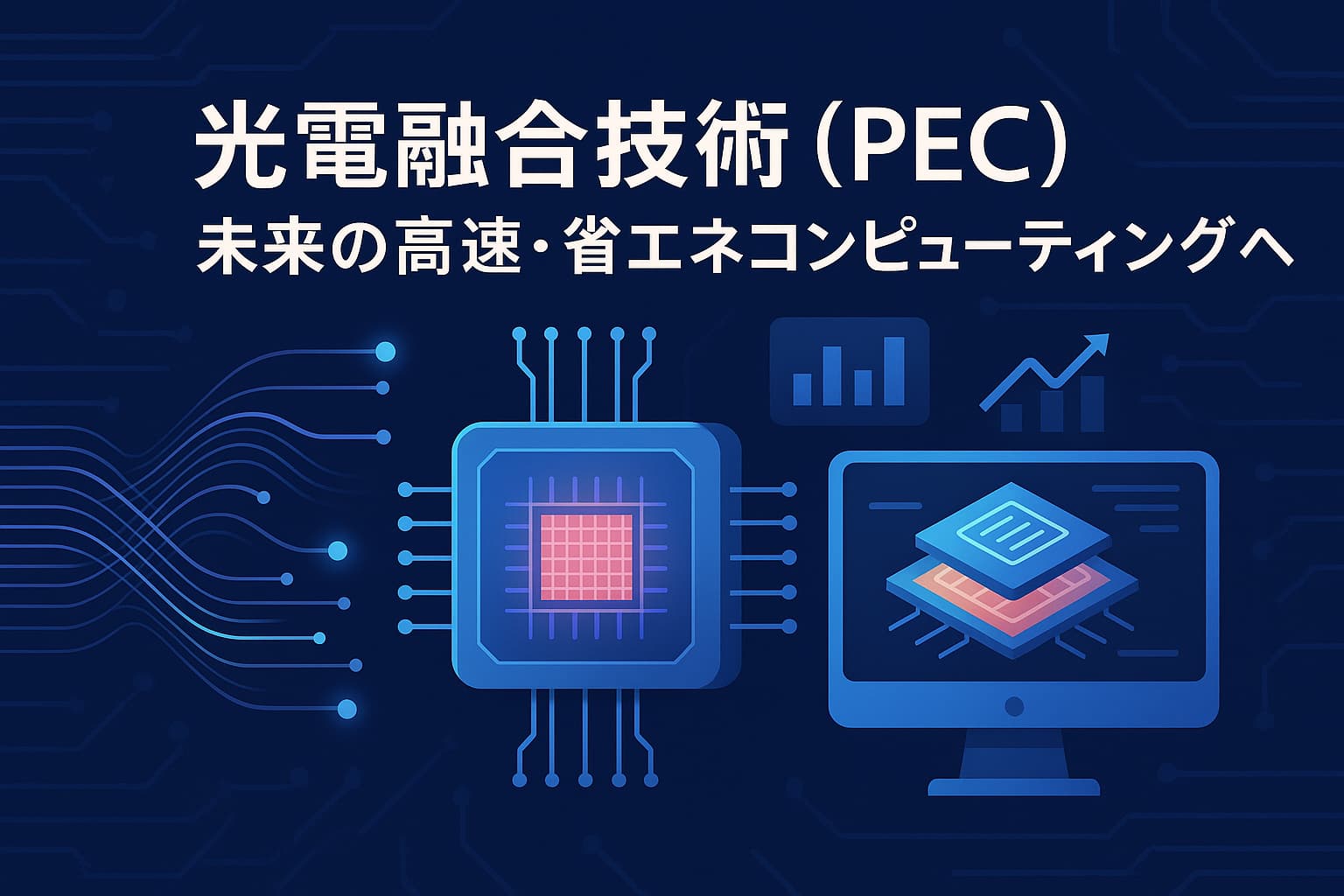近年インターネットやAIの急拡大に伴い、データ通信と処理の高速化・省エネ化が求められています。そこで注目されるのが、光電融合技術(Photonic‑Electronics Convergence, PEC)。これは、電気回路で演算し、光回路で伝送するシームレスな融合技術であり、NTTのIOWN構想を筆頭に世界中で研究・標準化が進んでいます。
🌟 なぜ光電融合が注目されるのか?
私たちが日常的に利用するスマートフォン、動画配信サービス、クラウド、AIアプリケーション──これらすべては背後で膨大なデータ通信と演算処理を必要としています。そして、この情報爆発の時代において、大量のデータを高速・低遅延かつ低消費電力で処理・転送することは極めて重要な課題となっています。
従来の電子回路(エレクトロニクス)では、データ伝送の際に電気信号の抵抗・発熱・ノイズといった物理的限界が付きまとい、特に大規模データセンターでは消費電力や冷却コストの増大が深刻な問題になっています。
以下は、光電融合技術が注目される主要な理由です:
1. 電力消費の大幅削減が可能
データセンターでは、CPUやメモリの演算処理だけでなく、それらをつなぐ配線・インターコネクトの電力消費が非常に大きいとされています。
光信号を使えば、配線における伝送損失が激減し、発熱も抑えられるため、冷却装置の稼働も抑えることができます。
例えば、NTTのIOWN構想では、現在のインターネットと比較して、
- 消費電力を100分の1に、
- 遅延を1/200に、
- 伝送容量を125倍にする という目標を掲げており、これはまさに光電融合が実現のカギとなる技術です。
2. AI・IoT時代に求められる超低遅延性
リアルタイム性が重要な自動運転、遠隔医療、産業用ロボット、メタバースなどの分野では、数ミリ秒以下の応答時間(レイテンシ)が求められます。
従来の電気信号では、長距離通信や複数のノードを介した接続により遅延や信号の揺らぎが発生してしまいます。
光通信を組み込むことで、信号の遅延を物理的に短縮できるため、リアルタイム応答性が飛躍的に高まります。
特に、光電融合で「チップ内」や「チップ間」の通信まで光化できれば、従来のボトルネックが根本的に解消される可能性があります。
3. 大容量・高帯域化に対応できる唯一の選択肢
AI処理やビッグデータ分析では、1秒あたり数百ギガビット、あるいはテラビットを超えるデータのやり取りが当たり前になります。
こうした爆発的な帯域要求に対し、光通信は非常に広い周波数帯(数百THz)を使えるため、電気では実現できない圧倒的な情報密度での伝送が可能です。
さらに、波長多重(WDM)などの技術を組み合わせれば、1本の光ファイバーで複数の信号を並列伝送することもでき、スケーラビリティの面でも大きな優位性を持っています。
4. チップレット技術・3D集積との相性が良い
近年の半導体開発では、単一の巨大チップを作るのではなく、複数の小さなチップ(チップレット)を組み合わせて高性能を実現するアーキテクチャが主流になりつつあります。
このチップレット間を電気で接続する場合、ボトルネックになりやすいのが通信部分です。
ここに光電融合を適用することで、チップ間の高スループット通信を実現でき、次世代CPUやAIアクセラレータの開発にも重要な役割を果たします。
すでにNVIDIAやライトマターなどの企業がこの領域に本格参入しています。
5. 持続可能なIT社会の実現に向けて
世界中のエネルギー問題、CO₂排出削減目標、そしてESG投資の拡大──これらの観点からも、ITインフラの省電力化は無視できないテーマです。
光電融合は単なる技術進化ではなく、環境と経済の両立を目指す社会的要請にも応える技術なのです。
🧩 PECの4段階ロードマップ(PEC‑1〜PEC‑4)
NTTが提唱するIOWN構想では、光と電気の融合(PEC:Photonic-Electronic Convergence)を段階的に社会実装していくために、4つのフェーズから成る技術ロードマップが描かれています。
このPECロードマップは、単なる回路設計の変更ではなく、情報通信インフラ全体の抜本的な見直しと位置づけられており、2030年代を見据えた長期的な国家・業界レベルの戦略に基づいています。
それぞれのステージで「どのレイヤーを光化するか」が変化していく点に注目してください。
| ステージ | 領域 | 内容 | 予定時期 |
|---|---|---|---|
| PEC‑1 | ネットワーク | データセンター間の光通信化(APN商用化) | 既に実施 |
| PEC‑2 | ボード間 | サーバー/ネットワーク機器間ボード光化 | ~2025年 |
| PEC‑3 | チップ間 | チップレット光接続による高速転送 | 2025〜2028年 |
| PEC‑4 | チップ内 | CPUコア内の光配線で演算まで光化 | 2028〜2032年+ |
🔹 PEC‑1:ネットワークレベルの光化(APN)【〜現在】
- 概要:最初の段階では、データセンター間や都市間通信など、長距離ネットワーク伝送に光技術を導入します。すでに商用化が進んでおり、IOWNの第1フェーズにあたります。
- 技術的特徴:
- 光ファイバー+光パケット伝送(APN: All-Photonics Network)
- デジタル信号処理(DSP)付きの光トランシーバー活用
- WDM(波長分割多重)による1本の線で複数の通信路
- 利点:
- 帯域幅の拡張
- 長距離通信における遅延の最小化(特にゲームや金融などに効果)
- 実績:
- 2021年よりNTTが試験導入を開始し、2023年から企業向けに展開
- NTTコミュニケーションズのAPNサービスとして一部稼働中
🔹 PEC‑2:ボードレベルの光電融合【2025年ごろ】
- 概要:2段階目では、サーバーやスイッチ内部のボード同士の接続を光化します。ここでは、距離は数十cm〜数mですが、データ量が爆発的に多くなるため、消費電力と発熱の削減が極めて重要です。
- 技術的特徴:
- コパッケージド・オプティクス(CPO:Co-Packaged Optics)の導入
- 光トランシーバとASICを同一基板上に配置
- 光配線を用いたボード間通信
- 利点:
- スイッチ機器の消費電力を最大80%削減
- システム全体の冷却コストを大幅に抑制
- 通信エラーの減少
- 主な企業動向:
- NVIDIAがCPO技術搭載のデータセンタースイッチを2025年に発売予定
- NTTはIOWN 2.0としてPEC‑2の社会実装を計画中
🔹 PEC‑3:チップ間の光化【2025〜2028年】
- 概要:3段階目では、1つのパッケージ内にある複数のチップ(チップレット)間を光で接続します。これにより、次世代のマルチチップ型CPU、AIプロセッサ、アクセラレータの性能を飛躍的に引き上げることが可能となります。
- 技術的特徴:
- 光I/Oチップ(光入出力コア)の開発
- シリコンフォトニクスと高密度配線のハイブリッド設計
- 超小型のマイクロ光導波路を使用
- 利点:
- チップレット間通信のボトルネックを解消
- 高スループットで低レイテンシな並列処理
- 複雑な3D集積回路の実現が容易に
- 活用例:
- AIアクセラレータ(例:推論・学習チップ)の高速化
- 医療画像処理や科学シミュレーションへの応用
🔹 PEC‑4:チップ内の光化【2028〜2032年】
- 概要:最終フェーズでは、CPUやAIプロセッサの内部配線(コアとコア間、キャッシュ間など)にも光信号を導入します。つまり、演算を行う「脳」そのものが光を使って情報を伝えるようになるという画期的な段階です。
- 技術的特徴:
- 光論理回路(フォトニックロジック)や光トランジスタの実装
- チップ内の情報伝達路すべてを光導波路で構成
- 位相・偏波制御による論理演算の最適化
- 利点:
- 熱によるスローダウン(サーマルスロットリング)の回避
- チップ全体の動作速度向上(GHz→THz級へ)
- システム規模に比例してスケーラブルな性能
- 研究段階:
- 産総研、NTTデバイス、PETRA、NEDOなどが先行開発中
- 10年スパンでの実用化が目指されている
🧭 ロードマップ全体を通じた目標
NTTが掲げるIOWNビジョンによれば、これらPECステージを通じて達成されるのは以下のような次世代情報インフラの姿です:
- 伝送容量:現在比125倍
- 遅延:現在比1/200
- 消費電力:現在比1/100
- スケーラビリティ:1デバイスあたりTbps〜Pbps級の通信
このように、PECの4段階は単なる半導体の進化ではなく、地球規模で持続可能な情報社会へのシフトを可能にする基盤技術なのです。
🏭 各社の取り組み・最新事例
光電融合(PEC)は、NTTをはじめとする日本企業だけでなく、世界中の大手IT企業やスタートアップ、大学・研究機関までもが関わるグローバルな技術競争の最前線にあります。
ここでは、各社がどのようにPECの開発・商用化を進めているか、代表的な動きを紹介します。
✔️ NTTグループ:IOWN構想の中核を担う主導者
- IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想のもと、PECの4段階導入を掲げ、APN(All Photonics Network)や光電融合チップの研究開発を推進。
- NTTイノベーティブデバイス(NID)を設立し、PEC実装をハードウェアレベルで担う。光I/Oコア、シリコンフォトニクスなどで2025年商用化を目指す。
- 2025年の大阪・関西万博では、IOWN技術を使ったスマート会場体験の提供を計画中。実証フィールドとして世界から注目されている。
🧪 注目技術:
- メンブレン型半導体レーザー
- 光トランジスタ
- シリコンフォトニクス+電気LSIのハイブリッドパッケージ
🧪 NVIDIA:次世代データセンターでのCPO導入
- 高性能GPUのリーダーであるNVIDIAは、光インターコネクトに強い関心を持ち、CPO(Co-Packaged Optics)への取り組みを強化。
- 2025年に予定されている次世代データセンタースイッチでは、光トランシーバをASICと同一パッケージに搭載することで、従来の電気配線の課題を根本的に解決。
- メリットは「スイッチポート密度向上」「消費電力抑制」「冷却効率向上」など。光配線技術がGPUクラスタの拡張に直結する。
📊 ビジネス的インパクト:
- HPC/AIクラスタ向けインターコネクト市場を狙う
- 将来的にはNVIDIA Grace Hopper系統のSoCとも統合可能性
🧪 Lightmatter(米国):AIと光電融合の統合戦略
- 2017年創業のスタートアップで、光によるAI推論処理チップと光通信を同一パッケージに統合。
- フォトニックプロセッサ「Envise」は、AIモデルの前処理・後処理を電気で、行列演算のコアを光で行うハイブリッド設計。
- さらに、光スイッチFabric「Passage」も開発しており、チップレット構成における光配線による柔軟な接続構造を提案。
➤ ロードマップ:
- 2025年夏:光AIチップ商用化予定
- 2026年:3D積層型光電融合モジュールを展開
🧪 Intel:シリコンフォトニクスの量産体制構築
- 2010年代から光トランシーバや光I/O製品の商用化を行っており、データセンター向けに広く出荷。
- PEC技術の先進的応用として、チップレット間接続や冷却機構と組み合わせた3D光パッケージの開発にも力を入れている。
- 大手クラウドベンダー(Hyperscaler)と提携し、100G/400G光I/Oの開発と製造を拡大中。
🔧 実績:
- 100G PSM4モジュール
- Coherent光トランシーバ(CPO設計)
🧪 産総研(AIST):国内の基礎研究・標準化をリード
- フォトニクス・エレクトロニクス融合研究センター(PEIRC)を設立。PECに必要な光導波路、光スイッチ、フォトニック集積回路を網羅的に研究。
- 量産を見据えた高信頼・高密度光実装技術や、光I/Oコアチップなどのコンソーシアムも支援。
🧪 産学連携:
- NEDO、PETRA、大学、民間企業と連携し国際標準策定にも貢献
- 日本のPECロードマップ立案において中心的役割
📊 その他の主要プレイヤー・動向
- Broadcom/Cisco:400G/800Gトランシーバを軸にCPOに向けた研究を強化。
- 中国勢(華為・中興):光I/Oやチップパッケージ特許申請が活発。中国内でのPEC技術独自育成を目指す。
- EU/IMEC/CEA-Leti:エネルギー効率の高いフォトニックアクセラレータの共同研究プロジェクトが複数進行中。
✔️ まとめ:技術競争と共創の時代へ
光電融合(PEC:Photonic-Electronic Convergence)は、単なる技術革新の1つにとどまらず、今後の情報社会の構造そのものを変革する起爆剤として注目されています。
本記事を通じて紹介したとおり、PECはNTTのIOWN構想をはじめ、NVIDIAやIntel、産総研、Lightmatterといった国内外の主要プレイヤーが、それぞれの強みを生かして段階的な社会実装と技術開発を進めています。
✔️ なぜ今、光電融合なのか?
私たちはいま、「限界を迎えつつある電気回路の時代」から、「光が支える新しい計算・通信インフラ」への転換点に立っています。
スマートフォンやクラウドサービス、生成AIなど、利便性が高まる一方で、それを支えるインフラは電力消費の増大、物理限界、冷却コストの上昇といった深刻な課題に直面しています。
光電融合は、こうした課題を根本から解決する手段であり、しかもそれを段階的に社会へ導入するための技術ロードマップ(PEC-1〜PEC-4)まで明確に描かれています。これは、革新でありながらも「現実的な未来」でもあるのです。
✔️ 技術競争だけでなく「共創」が鍵
世界中のIT企業・半導体メーカー・研究機関が、この領域で激しい競争を繰り広げています。
NVIDIAはデータセンター市場での覇権を視野に入れたCPO技術を、Lightmatterは光演算と通信の一体化によってAI領域の最適解を提示し、Intelは長年の光トランシーバ開発をベースに量産体制を築こうとしています。
一方、NTTや産総研を中心とする日本勢も、独自の強みで世界に挑んでいます。
しかし、光電融合という分野は、電気・光・材料・設計・ソフトウェア・システム工学といった多層的な知識・技術の統合が必要な領域です。
1つの企業・研究機関では完結できないため、いま求められているのは、国境や業界の垣根を超えた「共創」なのです。
✔️ 私たちの未来とどう関係するのか?
PECは一般消費者の目に触れることは少ない技術です。しかし、今後数年のうちに、以下のような変化を私たちは日常の中で体験することになるでしょう:
- ✔️ 動画の読み込みが瞬時に終わる
- ✔️ 遠隔医療や遠隔操作がストレスなく利用できる
- ✔️ AIとの対話が人間と変わらないほど自然になる
- ✔️ データセンターがより環境にやさしく、電力使用量が削減される
これらはすべて、裏側で動く情報処理・伝送技術が劇的に進化することによって初めて実現できる世界です。
🏁 結びに
光電融合は、単なる“未来の技術”ではありません。すでにPEC-1は現実となり、PEC-2〜4へ向けた準備も着々と進んでいます。
この技術が本格的に普及することで、私たちの社会インフラ、産業構造、ライフスタイルまでもが大きく変化していくことは間違いありません。
これからの数年、どの企業が主導権を握るのか、どの国が標準を制するのか──その動きに注目することは、未来を読み解くうえで非常に重要です。
そして、その未来は意外とすぐそばに迫っているのです。
光と電気が融合する時代──それは、持続可能で豊かな情報社会への第一歩です。
📚 参考文献
- NTT|IOWN構想と光電融合技術の紹介
https://group.ntt/jp/magazine/blog/photonics_electronics_convergence/ - NTT|IOWN構想に関する記者会見要旨
https://group.ntt/jp/magazine/blog/photonics_electronics_convergence_pressconference/ - 日経クロステック|光電融合が描く2030年の情報処理インフラ(前編)
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/10869/ - 日経クロステック|光電融合が描く2030年の情報処理インフラ(後編)
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/10923/ - NTTデバイス技術ジャーナル|光電融合技術の中核:光I/Oコアチップ
https://www.rd.ntt/iown_tech/post_6.html - 東京エレクトロン技術館|未来を担う光電融合の技術的意義と展望
https://www.tel.co.jp/museum/magazine/report/202308_01/ - 日立ハイテク|Photonic-Electronic Convergence(PEC)の研究開発動向
https://biz.hitachi-hightech.com/jp/column/tech/2023/07/24/pec.html - 産業技術総合研究所(AIST)|フォトニクス・エレクトロニクス融合研究センター(PEIRC)
https://unit.aist.go.jp/peirc/ - note|日本の情報処理基盤はどう変わる?光電融合技術の全体像
https://note.com/yaandyu0423/n/n8aae5a1a5976 - DLRIレポート|光電融合とデータセンターの未来
https://www.dlri.co.jp/report/ld/374525.html - 光と電子の融合技術の最新動向(IEICE論文より)
https://app.journal.ieice.org/trial/105_11/k105_11_1284/index.html - ogawahirofumi.com|PEC(光電融合)とは何かをわかりやすく解説
https://ogawahirofumi.com/optical-electronics-convergence-technology-iown/