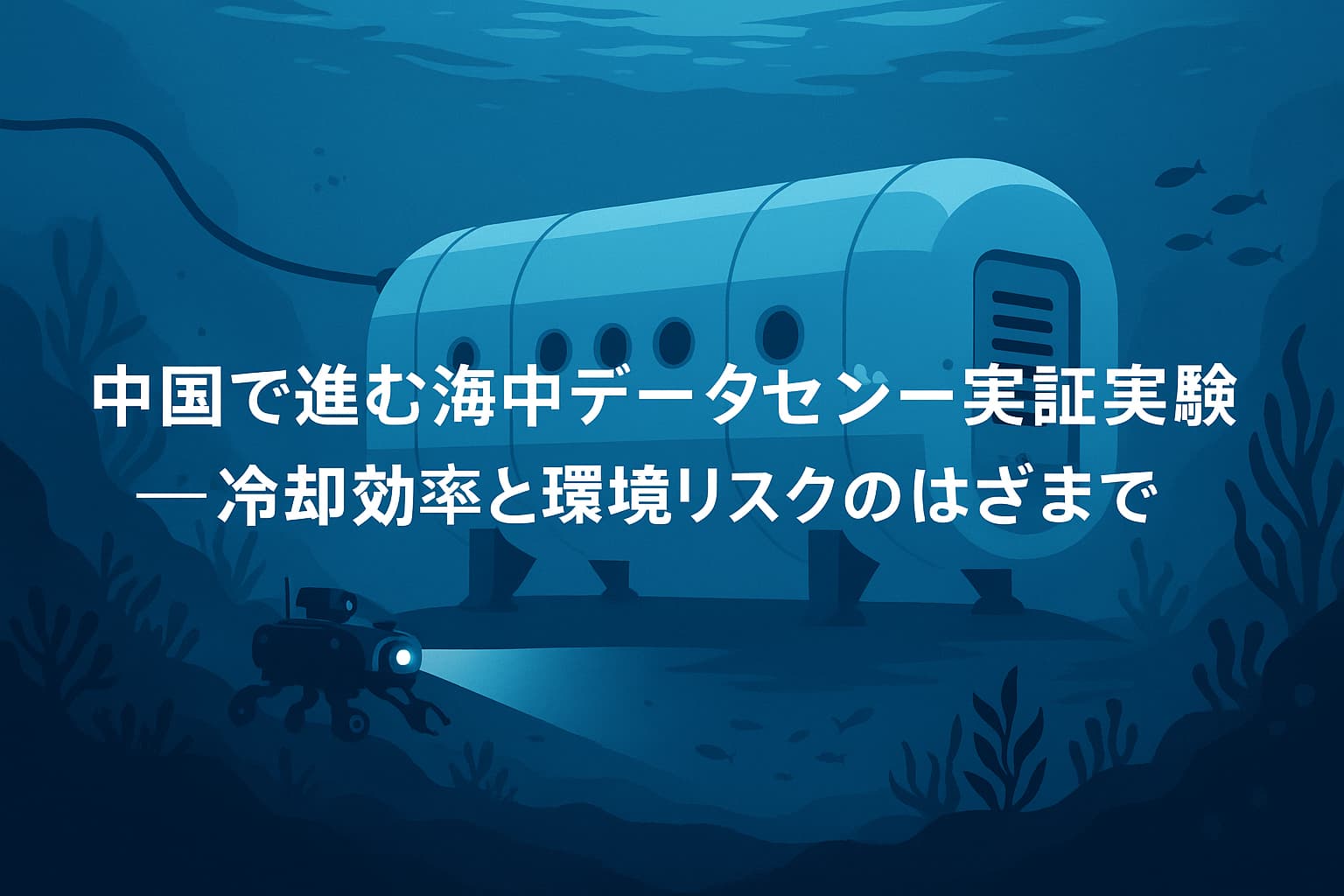世界的にデータセンターの電力消費量が急増しています。AIの学習処理やクラウドサービスの普及によってサーバーは高密度化し、その冷却に必要なエネルギーは年々増大しています。特に近年では、生成AIや大規模言語モデルの普及により、GPUクラスタを用いた高出力計算が一般化し、従来のデータセンターの冷却能力では追いつかない状況になりつつあります。
中国も例外ではありません。国内ではAI産業を国家戦略の柱と位置づけ、都市ごとにAI特区を設けるなど、膨大なデータ計算基盤を整備しています。その一方で、石炭火力への依存度が依然として高く、再生可能エネルギーの供給網は地域ごとに偏りがあります。加えて、北京や上海などの都市部では土地価格と電力コストが上昇しており、従来型のデータセンターを都市近郊に増設することは難しくなっています。
また、国家として「カーボンピークアウト(2030年)」「カーボンニュートラル(2060年)」を掲げていることもあり、電力効率の悪い施設は社会的にも批判の対象となっています。
こうした背景のもと、中国は冷却効率の抜本的な改善を目的として、海洋を活用したデータセンターの実証実験に踏み切りました。海中にサーバーポッドを沈め、自然の冷却力で電力消費を抑える構想は、環境対策とインフラ整備の両立を狙ったものです。
この試みは、Microsoftがかつて行った「Project Natick」から着想を得たとされ、中国版の海中データセンターとして注目を集めています。国家的なエネルギー転換の圧力と、AIインフラの急拡大という二つの要請が交差したところに、このプロジェクトの背景があります。
海中データセンターとは
海中データセンターとは、サーバーやストレージ機器を収容した密閉型の容器(ポッド)を海中に沈め、周囲の海水を自然の冷媒として活用するデータセンターのことです。
地上のデータセンターが空気や冷却水を使って熱を逃がすのに対し、海中型は海水そのものが巨大なヒートシンクとして働くため、冷却効率が飛躍的に高まります。特に深度30〜100メートル程度の海水は温度が安定しており、外気温の変化や季節に左右されにくいという利点があります。
中国でこの構想を推進しているのは、電子機器メーカーのハイランダー(Highlander Digital Technology)などの企業です。
同社は2024年以降、上海沖や海南島周辺で複数の実験モジュールを設置しており、将来的には数百台規模のサーバーモジュールを連結した商用海中データセンター群の建設を目指していると報じられています。これらのポッドは円筒状で、内部は乾燥した窒素などで満たされ、空気循環の代わりに液冷・伝導冷却が採用されています。冷却後の熱は外殻を通じて海水へ放出され、ファンやチラーの稼働を最小限に抑える仕組みです。
この方式により、冷却電力を従来比で最大90%削減できるとされ、エネルギー効率を示す指標であるPUE(Power Usage Effectiveness)も大幅に改善できると見込まれています。
また、騒音が発生せず、陸上の景観や土地利用にも影響を与えないという副次的な利点もあります。
他国・企業での類似事例
Microsoft「Project Natick」(米国)
海中データセンターという概念を実用段階まで検証した最初の大規模プロジェクトは、米Microsoftが2015年から2020年にかけて実施した「Project Natick(プロジェクト・ナティック)」です。
スコットランド沖のオークニー諸島近海で実験が行われ、12ラック・約864台のサーバーを収めた長さ12メートルの金属ポッドを水深35メートルに沈め、2年間にわたり稼働実験が行われました。この実験では、海中環境の安定した温度と低酸素環境がハードウェアの故障率を地上の1/8にまで低減させたと報告されています。また、メンテナンスが不要な完全密閉運用が成立することも確認され、短期的な成果としては極めて成功した例といえます。
ただし、商用化には至らず、Microsoft自身もその後は地上型・液冷型の方に研究重点を移しており、現時点では技術的概念実証(PoC)止まりです。
日本国内での動向
日本でもいくつかの大学・企業が海洋資源活用や温排水利用の観点から同様の研究を進めています。特に九州大学やNTTグループでは、海洋温度差発電や海水熱交換技術を応用した省エネルギーデータセンターの可能性を検討しています。
ただし、海中に沈設する実証実験レベルのものはまだ行われておらず、法制度面の整備(海洋利用権、環境影響評価)が課題となっています。
北欧・ノルウェーでの試み
冷却エネルギーの削減という目的では、ノルウェーのGreen Mountain社などが北海の海水を直接冷却に利用する「シーウォーター・クーリング方式」を実用化しています。
これは海中設置ではなく陸上型施設ですが、冷却水を海から直接引き込み、排水を温度管理して戻す構造です。PUEは1.1以下と極めて高効率で、「海の冷却力を利用する」という発想自体は世界的に広がりつつあることがわかります。
中国がこの方式に注目する理由
中国は、地上のデータセンターでは電力・土地・環境規制の制約が強まっている一方で、沿岸部に広大な海域を有しています。
政府が推進する「新型インフラ建設(新基建)」政策の中でも、データセンターのエネルギー転換は重点項目のひとつに挙げられています。
海中設置であれば、
- 冷却コストを劇的に減らせる
- 都市部の電力負荷を軽減できる
- 再生可能エネルギー(洋上風力)との併用が可能 といった利点を得られるため、国家戦略と整合性があるのです。
そのため、この技術は単なる実験的挑戦ではなく、エネルギー・環境・データ政策の交差点として位置づけられています。中国政府が海洋工学とITインフラを融合させようとする動きの象徴ともいえるでしょう。
消費電力削減の仕組み
データセンターにおける電力消費の中で、最も大きな割合を占めるのが「冷却」です。
一般的な地上型データセンターでは、サーバー機器の消費電力のほぼ同等量が冷却設備に使われるといわれており、総電力量の30〜40%前後が空調・冷却に費やされています。この冷却負荷をどれだけ減らせるかが、エネルギー効率の改善と運用コスト削減の鍵となります。海中データセンターは、この冷却部分を自然環境そのものに委ねることで、人工的な冷却装置を最小限に抑えようとする構想です。
冷却においてエネルギーを使うのは、主に「熱を空気や水に移す工程」と「その熱を外部へ放出する工程」です。海中では、周囲の水温が一定かつ低く、さらに水の比熱と熱伝導率が空気よりもはるかに高いため、熱の移動が極めて効率的に行われます。
1. 海水の熱伝導を利用した自然冷却
空気の熱伝導率がおよそ0.025 W/m·Kであるのに対し、海水は約0.6 W/m·Kとおよそ20倍以上の伝熱性能を持っています。そのため、サーバーの発熱を外部へ逃がす際に、空気よりも格段に少ない温度差で効率的な放熱が可能です。
また、深度30〜100メートルの海域は、外気温や日射の影響を受けにくく、年間を通じてほぼ一定の温度を保っています。
この安定した熱環境こそが、冷却制御をシンプルにし、ファンやチラーをほとんど稼働させずに済む理由です。海中データセンターの内部では、サーバーラックから発生する熱を液体冷媒または伝熱プレートを介して外殻部に伝え、外殻が直接海水と接触することで熱を放出します。これにより、冷媒を循環させるポンプや冷却塔の負荷が極めて小さくなります。
結果として、従来の地上型と比べて冷却に必要な電力量を最大で90%削減できると試算されています。
2. PUEの改善と運用コストへの影響
データセンターのエネルギー効率を示す指標として「PUE(Power Usage Effectiveness)」があります。
これは、
PUE = データセンター全体の電力消費量 ÷ IT機器(サーバー等)の電力消費量
で定義され、値が1.0に近いほど効率が高いことを意味します。
一般的な地上型データセンターでは1.4〜1.7程度が標準値ですが、海中データセンターでは1.1前後にまで改善できる可能性があるとされています。
この差は、単なる数値上の効率だけでなく、経済的にも大きな意味を持ちます。冷却機器の稼働が少なければ、設備の維持費・点検費・更新費も削減できます。
また、空調のための空間が不要になることで、サーバー密度を高められるため、同じ筐体容積でより多くの計算処理を行うことができます。
その結果、単位面積あたりの計算効率(computational density)も向上します。
3. 熱の再利用と環境への応用
さらに注目されているのが、海中で発生する「廃熱」の再利用です。
一部の研究機関では、海中ポッドの外殻で温められた海水を、養殖場や海藻栽培の加温に利用する構想も検討されています。北欧ではすでに陸上データセンターの排熱を都市暖房に転用する例がありますが、海中型の場合も地域の海洋産業との共生が模索されています。
ただし、廃熱量の制御や生態系への影響については、今後の実証が必要です。
4. 再生可能エネルギーとの統合
海中データセンターの構想は、エネルギー自給型の閉じたインフラとして設計される傾向があります。
多くの試験事例では、海上または沿岸部に設置した洋上風力発電や潮流発電と連携し、データセンターへの給電を行う計画が検討されています。海底ケーブルを通じて給電・通信を行う仕組みは、既存の海底通信ケーブル網と技術的に親和性が高く、設計上も現実的です。再生可能エネルギーとの統合によって、発電から冷却までをすべて自然エネルギーで賄える可能性があり、実質的なカーボンニュートラル・データセンターの実現に近づくと期待されています。
中国がこの方式を国家レベルの実証にまで進めた背景には、単なる冷却効率の追求だけでなく、エネルギー自立と環境対応を同時に進める狙いがあります。
5. 冷却に伴う課題と限界
一方で、海中冷却にはいくつかの技術的な限界も存在します。
まず、熱交換効率が高い反面、放熱量の制御が難しく、局所的な海水温上昇を招くリスクがあります。また、長期間の運用では外殻に生物が付着して熱伝導を妨げる「バイオファウリング」が起こるため、定期的な清掃や薬剤処理が必要になります。これらは冷却効率の低下や外殻腐食につながり、長期安定運用を阻害する要因となります。そのため、現在の海中データセンターはあくまで「冷却効率の実証」と「構造耐久性の検証」が主目的であり、商用化にはなお課題が多いのが実情です。
しかし、もしこれらの問題が克服されれば、従来型データセンターの構造を根本から変える革新的な技術となる可能性があります。
技術的なリスク
海中データセンターは、冷却効率やエネルギー利用の面で非常に魅力的な構想ではありますが、同時に多層的な技術リスクを抱えています。特に「長期間にわたって無人で安定稼働させる」という要件は、既存の陸上データセンターとは根本的に異なる技術課題を伴います。ここでは、主なリスク要因をいくつかの視点から整理します。
1. 腐食と耐久性の問題
最も深刻なリスクの一つが、海水による腐食です。海水は塩化物イオンを多く含むため、金属の酸化を急速に進行させます。
特に、鉄系やアルミ系の素材では孔食(ピッティングコロージョン)やすきま腐食が生じやすく、短期間で構造的な強度が失われる恐れがあります。そのため、外殻には通常、ステンレス鋼(SUS316L)、チタン合金、あるいはFRP(繊維強化プラスチック)が使用されます。
また、異なる金属を組み合わせると電位差による電食(ガルバニック腐食)が発生するため、素材選定は非常に慎重を要します。
さらに、電食対策として犠牲陽極(カソード防食)を設けることも一般的ですが、長期間の運用ではこの陽極自体が消耗し、交換が必要になります。
海底での交換作業は容易ではなく、結果的にメンテナンス周期が寿命を左右することになります。
2. シーリングと内部環境制御
海中ポッドは完全密閉構造ですが、長期運用ではシーリング(パッキン)材の劣化も大きな問題です。
圧力差・温度変化・紫外線の影響などにより、ゴムや樹脂製のシールが徐々に硬化・収縮し、微細な水分が内部に侵入する可能性があります。この「マイクロリーク」によって内部の湿度が上昇すると、電子基板の腐食・絶縁破壊・結露といった致命的な障害を引き起こします。
また、内部は気体ではなく乾燥窒素や不活性ガスで満たされていることが多く、万が一漏れが発生するとガス組成が変化して冷却性能や安全性が低下します。
したがって、シーリング劣化の早期検知・圧力変化の監視といった環境モニタリング技術が不可欠です。
3. 外力による構造損傷
海中という環境では、潮流・波浪・圧力変化などの外的要因が常に作用します。
特に、海流による定常的な振動(vortex-induced vibration)や、台風・地震などによる突発的な外力が構造体にストレスを与えます。金属疲労が蓄積すれば、溶接部や接合部に微細な亀裂が生じ、最終的には破損につながる可能性もあります。
また、海底の地形や堆積物の動きによってポッドの傾きや沈下が起こることも想定されます。設置場所が軟弱な海底であれば、スラスト(側圧)や沈降による姿勢変化が通信ケーブルに負荷を与え、断線や信号劣化の原因になるおそれもあります。
4. 生物・環境要因による影響
海中ではバイオファウリング(生物付着)と呼ばれる現象が避けられません。貝、藻、バクテリアなどが外殻表面に付着し、時間の経過とともに層を形成します。
これにより熱伝達効率が低下し、冷却能力が徐々に損なわれます。また、バクテリアによって金属表面に微生物腐食(MIC: Microbiologically Influenced Corrosion)が発生することもあります。
さらに、外殻の振動や電磁放射が一部の海洋生物に影響を与える可能性も指摘されています。特に、音波や電磁場に敏感な魚類・哺乳類への影響は今後の研究課題です。
一方で、海洋生物がケーブルや外殻を物理的に損傷させるリスクも無視できません。過去には海底ケーブルをサメが噛み切る事例も報告されています。
5. 通信・電力ケーブルのリスク
海中データセンターは、電力とデータ通信を海底ケーブルでやり取りします。
しかし、このケーブルは外力や漁業活動によって損傷するリスクが非常に高い部分です。実際、2023年には台湾・紅海・フィリピン周辺で海底ケーブルの断線が相次ぎ、広域通信障害を引き起こしました。多くは底引き網漁船の錨やトロール網による物理的損傷が原因とされています。ケーブルが切断されると、データ通信だけでなく電力供給も途絶します。
特に海中ポッドが複数連結される場合、1系統の断線が全モジュールに波及するリスクがあります。したがって、複数ルートの冗長ケーブルを設けることや、自動フェイルオーバー機構の導入が不可欠です。
6. メンテナンスと復旧の困難さ
最大の課題は、故障発生時の対応の難しさです。
陸上データセンターであれば、障害発生後すぐに技術者が現場で交換作業を行えますが、海中ではそうはいきません。不具合が発生した場合は、まず海上からROV(遠隔操作無人潜水機)を投入して診断し、必要に応じてポッド全体を引き揚げる必要があります。この一連の作業には天候・潮流の影響が大きく、場合によっては数週間の停止を余儀なくされることもあります。
さらに、メンテナンス中の潜水作業には常に人的リスクが伴います。深度が30〜50メートル程度であっても、潮流が速い海域では潜水士の減圧症・機器故障などの事故が起こる可能性があります。
結果として、海中データセンターの運用コストは「冷却コストの削減」と「保守コストの増加」のトレードオフ関係にあるといえます。
7. 冗長性とフェイルセーフ設計の限界
多くの構想では、海中データセンターを無人・遠隔・自律運転とする方針が取られています。
そのため、障害発生時には自動切替や冗長構成によるフェイルオーバーが必須となります。しかし、これらの機構を完全にソフトウェアで実現するには限界があります。たとえば、冷却系や電源系の物理的障害が発生した場合、遠隔制御での回復はほぼ不可能です。
また、長期にわたり閉鎖環境で稼働するため、センサーのキャリブレーションずれや通信遅延による監視精度の低下といった問題も無視できません。
8. 自然災害・地政学的リスク
技術的な問題に加え、自然災害も無視できません。地震や津波が発生した場合、海底構造物は陸上よりも被害の範囲を特定しづらく、復旧も長期化します。
また、南シナ海や台湾海峡といった地政学的に不安定な海域に設置される場合、軍事的緊張・領海侵犯・監視対象化といった政治的リスクも想定されます。特に国際的な海底通信ケーブル網に接続される構造であれば、安全保障上の観点からも注意が必要です。
まとめ ― 技術的完成度はまだ実験段階
これらの要素を総合すると、海中データセンターは現時点で「冷却効率の証明には成功したが、長期安定稼働の実績がない」段階にあります。
腐食・外力・通信・保守など、いずれも地上では経験のない性質のリスクであり、数年単位での実証が不可欠です。言い換えれば、海中データセンターの真価は「どれだけ安全に、どれだけ長く、どれだけ自律的に稼働できるか」で決まるといえます。
この課題を克服できれば、世界のデータセンターの構造を根本から変える可能性を秘めていますが、現段階ではまだ「実験的技術」であるというのが現実的な評価です。
環境・安全保障上の懸念
海中データセンターは、陸上の土地利用や景観への影響を最小限に抑えられるという利点がある一方で、環境影響と地政学的リスクの双方を内包する技術でもあります。
「海を使う」という発想は斬新である反面、そこに人類が踏み込むことの影響範囲は陸上インフラよりも広く、予測が難しいのが実情です。
1. 熱汚染(Thermal Pollution)
最も直接的な環境影響は、冷却後の海水が周囲の水温を上昇させることです。
海中データセンターは冷却効率が高いとはいえ、サーバーから発生する熱エネルギーを最終的には海水に放出します。そのため、長期間稼働すると周辺海域で局所的な温度上昇が起きる可能性があります。
例えば、Microsoftの「Project Natick」では、短期稼働中の周辺温度上昇は数度未満に留まりましたが、より大規模で恒常的な運用を行えば、海洋生態系の構造を変える可能性が否定できません。海中では、わずか1〜2℃の変化でもプランクトンの分布や繁殖速度が変化し、食物連鎖全体に影響することが知られています。特に珊瑚や貝類など、温度変化に敏感な生物群では死亡率の上昇が確認されており、海中データセンターが「人工的な熱源」として作用するリスクは無視できません。
さらに、海流が穏やかな湾内や浅海に設置された場合、熱の滞留によって温水域が形成され、酸素濃度の低下や富栄養化が進行する可能性もあります。
これらの変化は最初は局所的でも、長期的には周囲の海洋環境に累積的な影響を与えかねません。
2. 化学的・物理的汚染のリスク
海中構造物の防食や維持管理には、塗料・コーティング剤・防汚材が使用されます。
これらの一部には有機スズ化合物や銅系化合物など、生態毒性を持つ成分が含まれている場合があります。微量でも長期的に溶出すれば、底生生物やプランクトンへの悪影響が懸念されます。
また、腐食防止のために用いられる犠牲陽極(金属塊)が電解反応で徐々に溶け出すと、金属イオン(アルミニウム・マグネシウム・亜鉛など)が海水中に拡散します。これらは通常の濃度では問題になりませんが、大規模展開時には局地的な化学汚染を引き起こす恐れがあります。
さらに、メンテナンス時に発生する清掃用薬剤・防汚塗料の剥離物が海底に沈降すれば、海洋堆積物の性質を変える可能性もあります。
海中データセンターの「廃棄」フェーズでも、外殻や内部配線材の回収が完全でなければ、マイクロプラスチックや金属粒子の流出が生じる懸念も残ります。
3. 音響・電磁的影響
データセンターでは、冷却系ポンプや電源変換装置、通信モジュールなどが稼働するため、微弱ながらも音響振動(低周波ノイズ)や電磁波(EMI)が発生します。
これらは陸上では問題にならない程度の微小なものですが、海中では音波が長距離を伝わるため、イルカやクジラなど音響に敏感な海洋生物に影響を与える可能性があります。
また、給電・通信を担うケーブルや変圧設備が発する電磁場は、魚類や甲殻類などが持つ磁気感受受容器(magnetoreception)に干渉するおそれがあります。研究段階ではまだ明確な結論は出ていませんが、電磁ノイズによる回遊ルートの変化が観測された事例も存在します。
4. 環境影響評価(EIA)の難しさ
陸上のデータセンターでは、建設前に環境影響評価(EIA: Environmental Impact Assessment)が義務づけられていますが、海中構造物については多くの国で法的枠組みが未整備です。
海域の利用権や排熱・排水の規制は、主に港湾法や漁業法の範囲で定められているため、データセンターのような「電子インフラ構造物」を直接想定していません。特に中国の場合、環境影響評価の制度は整備されつつあるものの、海洋構造物の持続的な熱・化学的影響を評価する指標体系はまだ十分ではありません。
海洋科学的なデータ(潮流・海水温・酸素濃度・生態系モデル)とITインフラ工学の間には、依然として学際的なギャップが存在しています。
5. 領海・排他的経済水域(EEZ)の問題
安全保障の観点から見ると、ポッドが設置される位置とその管理責任が最も重要な論点です。
海中データセンターは原則として自国の領海またはEEZ内に設置されますが、海流や地震による地形変化で位置が移動する可能性があります。万が一ポッドが流出して他国の水域に侵入した場合、それが「商用施設」なのか「国家インフラ」なのかの区別がつかず、国際法上の解釈が曖昧になります。国連海洋法条約(UNCLOS)では、人工島や構造物の設置は許可制ですが、「データセンター」という新しいカテゴリは明示的に規定されていません。そのため、国家間でトラブルが発生した場合、法的な解決手段が確立していないという問題があります。
また、軍事的観点から見れば、海底に高度な情報通信装置が設置されること自体が、潜在的なスパイ活動や監視インフラと誤解される可能性もあります。特に南シナ海や台湾海峡といった地政学的に緊張の高い海域に設置される場合、周辺国との摩擦を生む要因となりかねません。
6. 災害・事故時の国際的対応
地震・津波・台風などの自然災害で海中データセンターが破損した場合、その影響は単一国の問題に留まりません。
漏電・油漏れ・ケーブル断線などが広域の通信インフラに波及する恐れがあり、国際通信網の安全性に影響を及ぼす可能性もあります。現行の国際枠組みでは、事故発生時の責任分担や回収義務を定めたルールが存在しません。
また、仮に沈没や破損が発生した場合、残骸が水産業・航路・海洋調査など他の産業活動に干渉することもあり得ます。
こうした事故リスクに対して、保険制度・国際的な事故報告基準の整備が今後の課題となります。
7. 情報安全保障上の懸念
もう一つの側面として、物理的なアクセス制御とサイバーセキュリティの問題があります。
海中データセンターは遠隔制御で運用されるため、制御系ネットワークが外部から攻撃されれば、電力制御・冷却制御・通信遮断などがすべて同時に起こる危険があります。
また、物理的な監視が困難なため、破壊工作や盗聴などを早期に検知することが難しく、陸上型よりも検知遅延リスクが高いと考えられます。特に国家主導で展開される海中データセンターは、外国政府や企業にとっては「潜在的な通信インフラのブラックボックス」と映りかねず、外交上の摩擦要因にもなり得ます。
したがって、国際的な透明性と情報共有の枠組みを設けることが、安全保障リスクを最小化する鍵となります。
まとめ ― 革新とリスクの境界線
海中データセンターは、エネルギー効率や持続可能性の面で新しい可能性を示す一方、環境と国際秩序という二つの領域にまたがる技術でもあります。
そのため、「どの国の海で」「どのような法制度のもとで」「どの程度の環境影響を許容して」運用するのかという問題は、単なる技術論を超えた社会的・政治的テーマです。冷却効率という数値だけを見れば理想的に思えるこの構想も、実際には海洋生態系の複雑さや国際法の曖昧さと向き合う必要があります。
技術的成果と環境的・地政学的リスクの両立をどう図るかが、海中データセンターが真に「持続可能な技術」となれるかを左右する分岐点といえるでしょう。
有人作業と安全性
海中データセンターという構想は、一般の人々にとって非常に未来的に映ります。
海底でサーバーが稼働し、遠隔で管理されるという発想はSF映画のようであり、「もし内部で作業中に事故が起きたら」といった想像を掻き立てるかもしれません。
しかし実際には、海中データセンターの設計思想は完全無人運用(unmanned operation)を前提としており、人が内部に入って作業することは構造的に不可能です。
1. 完全密閉構造と無人設計
海中データセンターのポッドは、内部に人が立ち入るための空間やライフサポート装置を持っていません。
内部は乾燥窒素や不活性ガスで満たされ、外部との気圧差が大きいため、人間が直接侵入すれば圧壊や酸欠の危険があります。したがって、設置後の運用は完全に遠隔制御で行われ、サーバーの状態監視・電力制御・温度管理などはすべて自動システムに委ねられています。Microsoftの「Project Natick」でも、設置後の2年間、一度も人が内部に入らずに稼働を続けたという記録が残っています。
この事例が示すように、海中データセンターは「人が行けない場所に置く」ことで、逆に信頼性と保全性を高めるという逆説的な設計思想に基づいています。
2. 人が関与するのは「設置」と「引き揚げ」だけ
人間が実際に作業に関わるのは、基本的に設置時と引き揚げ時に限られます。
設置時にはクレーン付きの作業船を用い、ポッドを慎重に吊り下げて所定の位置に沈めます。この際、潜水士が補助的にケーブルの位置確認や固定作業を行う場合もありますが、内部に入ることはありません。引き揚げの際も同様に、潜水士やROV(遠隔操作無人潜水機)がケーブルの取り外しや浮上補助を行います。これらの作業は、浅海域(深度30〜50メートル程度)で行われることが多く、技術的には通常の海洋工事の範囲内です。ただし、海況が悪い場合や潮流が速い場合には危険が伴い、作業中止の判断が求められます。
また、潮流や気象条件によっては作業スケジュールが数日単位で遅延することもあります。
3. 潜水士の安全管理とリスク
設置や撤去時に潜水士が関与する場合、最も注意すべきは減圧症(潜水病)です。
浅海とはいえ、長時間作業を続ければ血中窒素が飽和し、急浮上時に気泡が生じて体内を損傷する可能性があります。このため、作業チームは一般に「交代制」「安全停止」「水面支援(surface supply)」などの手順を厳守します。
また、作業員が巻き込まれるおそれがあるのは、クレーン吊り下げ時や海底アンカー固定時です。数トン単位のポッドが動くため、わずかな揺れやケーブルの張力変化が致命的な事故につながることがあります。
海洋工事分野では、これらのリスクを想定した作業計画書(Dive Safety Plan)の作成が義務づけられており、中国や日本でもISO規格や国家基準(GB/T)に基づく安全管理が求められます。
4. ROV(遠隔操作無人潜水機)の活用
近年では、潜水士に代わってROV(Remotely Operated Vehicle)が作業を行うケースが増えています。
ROVは深度100メートル前後まで潜行でき、カメラとロボットアームを備えており、配線確認・ケーブル接続・表面検査などを高精度に実施できます。これにより、人的リスクをほぼ排除しながらメンテナンスや異常検知が可能になりました。特にハイランダー社の海中データセンター計画では、ROVを使った自動点検システムの導入が検討されています。AI画像解析を用いてポッド外殻の腐食や付着物を検知し、必要に応じて自動洗浄を行うという構想も報じられています。
こうした技術が進めば、完全無人運用の実現性はさらに高まるでしょう。
5. 緊急時対応の難しさ
一方で、海中という環境特性上、緊急時の即応性は非常に低いという課題があります。
もし電源系統や冷却系統で深刻な故障が発生した場合、陸上からの再起動やリセットでは対応できないことがあります。その際にはポッド全体を引き揚げる必要がありますが、海況が悪ければ作業が数日間遅れることもあります。
また、災害時には潜水やROV作業自体が不可能となるため、異常を検知しても即時対応ができないという構造的な制約を抱えています。仮に沈没や転倒が発生した場合、内部データは暗号化されているとはいえ、装置回収が遅れれば情報資産の喪失につながる可能性もあります。
そのため、設計段階から自動シャットダウン機構や沈没時のデータ消去機能が組み込まれるケースもあります。
6. 安全規制と法的責任
海中での作業や構造物設置に関しては、各国の労働安全法・港湾法・海洋開発法などが適用されます。
しかし「データセンター」という業種自体が新しいため、法制度が十分に整備されていません。事故が起きた際に「海洋工事事故」として扱うのか、「情報インフラの障害」として扱うのかで、責任主体と補償範囲が変わる点も指摘されています。
また、無人運用を前提とした設備では、保守委託業者・船舶運用会社・通信事業者など複数の関係者が関与するため、事故時の責任分担が不明確になりやすいという問題もあります。特に国際的なプロジェクトでは、どの国の安全基準を採用するかが議論の対象になります。
7. フィクションとの対比 ― 現実の「安全のための無人化」
映画やドラマでは、海底施設に閉じ込められる研究者や作業員といった描写がしばしば登場します。しかし、現実の海中データセンターは「人を入れないことこそ安全である」という発想から設計されています。内部には通路も空間もなく、照明すら設けられていません。内部アクセスができないかわりに、外部の監視・制御・診断を極限まで自動化する方向で技術が発展しています。
したがって、「人が閉じ込められる」という映画的なシナリオは、技術的にも法的にも発生し得ません。むしろ、有人作業を伴うのは設置・撤去時の一時的な海洋作業に限られており、その安全確保こそが実際の運用上の最大の関心事です。
8. まとめ ― 安全性は「無人化」と「遠隔化」に依存
海中データセンターの安全性は、人が入ることを避けることで成立しています。
それは、潜水士を危険な環境に晒さず、メンテナンスを遠隔・自動化によって行うという方向性です。
一方で、完全無人化によって「緊急時の即応性」や「保守の柔軟性」が犠牲になるというトレードオフもあります。今後この分野が本格的に商用化されるためには、人が直接介入しなくても安全を維持できる監視・診断システムの確立が不可欠です。
無人化は安全性を高める手段であると同時に、最も難しい技術課題でもあります。海中データセンターの未来は、「人が行かなくても安全を確保できるか」という一点にかかっているといえるでしょう。
おわりに
海中データセンターは、冷却効率と電力削減という明確な目的のもとに生まれた技術ですが、その意義は単なる省エネの枠を超えています。
データ処理量が爆発的に増える時代において、電力や水資源の制約をどう乗り越えるかは、各国共通の課題となっています。そうした中で、中国が海洋という「未利用の空間」に活路を見いだしたことは、技術的にも戦略的にもきわめて示唆的です。
この構想は、AIやクラウド産業を国家の成長戦略と位置づける中国にとって、インフラの自立とエネルギー効率の両立を目指す試みです。国内の大規模AIモデル開発、クラウドプラットフォーム運営、5G/6Gインフラの拡張といった分野では、膨大な計算資源と電力が不可欠です。
その一方で、環境負荷の高い石炭火力への依存を減らすという政策目標もあり、「海を冷却装置として利用する」という発想は、その二律背反を埋める象徴的な解決策といえるでしょう。
技術革新としての意義
海中データセンターの研究は、冷却効率だけでなく、封止技術・耐腐食設計・自動診断システム・ROV運用といった複数の分野を横断する総合的な技術開発を促しています。
特に、長期間の密閉運用を前提とする点は、宇宙ステーションや極地観測基地などの閉鎖環境工学とも共通しており、今後は完全自律型インフラ(autonomous infrastructure)の実証フィールドとしても注目されています。「人が入らずに保守できるデータセンター」という概念は、陸上施設の無人化やAIによる自己診断技術にも波及するでしょう。
未解決の課題
一方で、現時点の技術的成熟度はまだ「実験段階」にあります。
腐食・バイオファウリング・ケーブル損傷・海流による振動など、陸上では想定しづらいリスクが多く存在します。また、障害発生時の復旧には天候や潮流の影響を受けやすく、運用コストの面でも依然として不確実な要素が残ります。冷却のために得た効率が、保守や回収で相殺されるという懸念も無視できません。
この技術が商用化に至るには、長期安定稼働の実績と、トータルコストの実証が不可欠です。
環境倫理と社会的受容
環境面の課題も避けて通れません。
熱汚染や化学汚染の懸念、電磁波や音響の影響、そして生態系の変化――
これらは数値上の効率だけでは測れない倫理的な問題を内包しています。技術が進歩すればするほど、その「副作用」も複雑化するのが現実です。データセンターが人間社会の神経系として機能するなら、その「血液」としての電力をどこで、どのように供給するのかという問いは、もはや技術者だけの問題ではありません。
また、国際的な法制度や環境影響評価の整備も急務です。海洋という公共空間における技術利用には、国際的な合意と透明性が欠かせません。もし各国が独自に海中インフラを設置し始めれば、資源開発と同様の競争や摩擦が生じる可能性もあります。
この点で、海中データセンターは「次世代インフラ」であると同時に、「新しい国際秩序の試金石」となる存在でもあります。
人と技術の関係性
興味深いのは、このプロジェクトが「人が立ち入らない場所で技術を完結させる」ことを目的としている点です。
安全性を確保するために人の介入を排除し、遠隔制御と自動運用で完結させる構想は、一見すると冷たい機械文明の象徴にも見えます。しかし、見方を変えればそれは、人間を危険から遠ざけ、より安全で持続的な社会を築くための一歩でもあります。
無人化とは「人を排除すること」ではなく、「人を守るために距離を取る技術」でもあるのです。
今後の展望
今後、海中データセンターの実用化が進めば、冷却問題の解決だけでなく、新たな海洋産業の創出につながる可能性があります。
海洋再生エネルギーとの統合、養殖業や温排水利用との共生、さらには災害時のバックアップ拠点としての活用など、応用の幅は広がっています。また、深海観測・通信インフラとの融合によって、地球規模での気候データ収集や地震観測への転用も考えられます。
このように、海中データセンターは単なる情報処理施設ではなく、地球環境と情報社会を結ぶインターフェースとなる可能性を秘めています。
結び
海中データセンターは、現代社会が抱える「デジタルと環境のジレンマ」を象徴する技術です。
それは冷却効率を追い求める挑戦であると同時に、自然との共生を模索する実験でもあります。海の静寂の中に置かれたサーバーポッドは、単なる機械の集合ではなく、人間の知恵と限界の両方を映す鏡と言えるでしょう。この試みが成功するかどうかは、技術そのものよりも、その技術を「どのように扱い」「どのように社会に組み込むか」という姿勢にかかっています。海を新たなデータの居場所とする挑戦は、私たちがこれからの技術と環境の関係をどう設計していくかを問う、時代的な問いでもあります。
海中データセンターが未来の主流になるか、それとも一過性の試みで終わるか――
その答えは、技術だけでなく、社会の成熟に委ねられています。
参考文献
- Microsoft finds underwater datacenters are reliable, practical and use energy sustainably
https://news.microsoft.com/source/features/sustainability/project-natick-underwater-datacenter/ - China Is Putting Data Centers in the Ocean to Keep Them Cool
https://www.scientificamerican.com/article/china-powers-ai-boom-with-undersea-data-centers/ - China deploys 1,400-ton commercial underwater data center
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/china-deploys-1400-ton-commercial-underwater-data-center/ - China’s underwater data center expanded
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/chinas-underwater-data-center-expanded/ - Project Natick: Microsoft’s underwater voyage of discovery
https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/project-natick-microsofts-underwater-voyage-discovery/ - China’s Highlander completes first commercial underwater data center, looks for exports
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/chinas-highlander-completes-first-commercial-underwater-data-center-looks-for-exports/ - HiCloud to develop offshore wind powered underwater data center off coast of Shanghai, China
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/hicloud-to-develop-offshore-wind-powered-underwater-data-center-off-coast-of-shanghai-china/ - Microsoft’s Underwater Data Center Makes Environmental Strides
https://www.cmswire.com/information-management/microsofts-underwater-data-center-makes-environmental-strides/