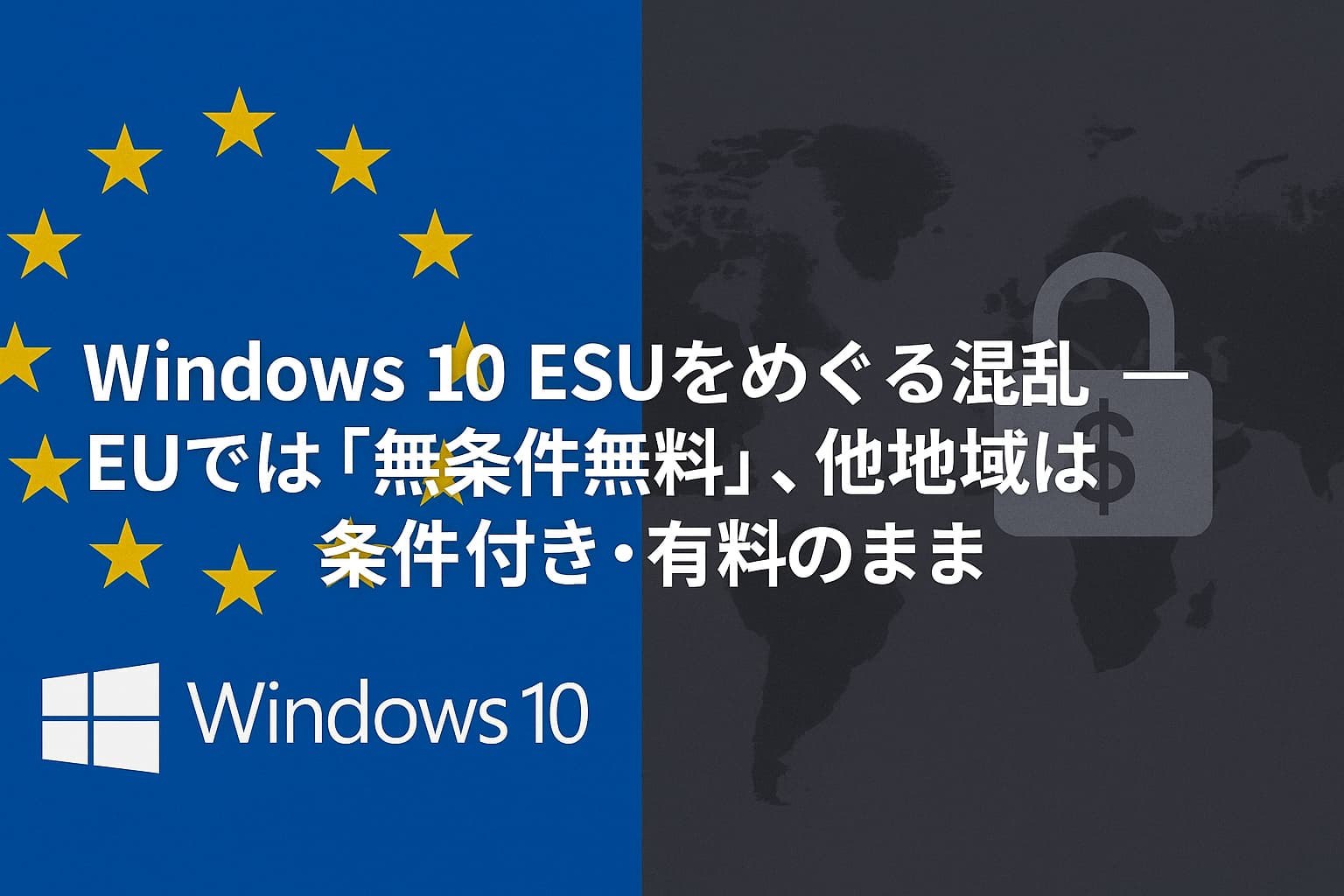2025年9月、Microsoftは世界中のWindows 10ユーザーに大きな影響を与える方針転換を発表しました。
Windows 10は2025年10月14日でサポート終了を迎える予定であり、これは依然として世界で数億台が稼働しているOSです。サポートが終了すれば、セキュリティ更新が提供されなくなり、利用者はマルウェアや脆弱性に対して無防備な状態に置かれることになります。そのため、多くのユーザーにとって「サポート終了後も安全にWindows 10を使えるかどうか」は死活的な問題です。
この状況に対応するため、Microsoftは Extended Security Updates(ESU)プログラム を用意しました。しかし、当初は「Microsoftアカウント必須」「Microsoft Rewardsなど自社サービスとの連携が条件」とされ、利用者にとって大きな制約が課されることが明らかになりました。この条件は、EUのデジタル市場法(DMA)やデジタルコンテンツ指令(DCD)に抵触するのではないかと批判され、消費者団体から強い異議申し立てが起こりました。
結果として、EU域内ではMicrosoftが大きく譲歩し、Windows 10ユーザーに対して「無条件・無料」での1年間のセキュリティ更新提供を認めるという異例の対応に至りました。一方で、米国や日本を含むEU域外では従来の条件が維持され、地域によって利用者が受けられる保護に大きな格差が生じています。
本記事では、今回の経緯を整理し、EUとそれ以外の地域でなぜ対応が異なるのか、そしてその背景にある規制や消費者運動の影響を明らかにしていきます。
背景
Windows 10 は 2015 年に登場して以来、Microsoft の「最後の Windows」と位置付けられ、長期的に改良と更新が続けられてきました。世界中の PC の大半で採用され、教育機関や行政、企業システムから個人ユーザーまで幅広く利用されている事実上の標準的な OS です。2025 年 9 月現在でも数億台規模のアクティブデバイスが存在しており、これは歴代 OS の中でも非常に大きな利用規模にあたります。
しかし、この Windows 10 もライフサイクルの終了が近づいています。公式には 2025 年 10 月 14 日 をもってセキュリティ更新が終了し、以降は既知の脆弱性や新たな攻撃に対して無防備になります。特に個人ユーザーや中小企業にとっては「まだ十分に動作している PC が突然リスクにさらされる」という現実に直面することになります。
これに対して Microsoft は従来から Extended Security Updates(ESU) と呼ばれる仕組みを用意してきました。これは Windows 7 や Windows Server 向けにも提供されていた延長サポートで、通常サポートが終了した OS に対して一定期間セキュリティ更新を提供するものです。ただし、原則として有償で、主に企業や組織を対象としていました。Windows 10 に対しても同様に ESU プログラムが設定され、個人ユーザーでも年額課金によって更新を継続できると発表されました。
ところが、今回の Windows 10 ESU プログラムには従来と異なる条件が課されていました。利用者は Microsoft アカウントへのログインを必須とされ、さらに Microsoft Rewards やクラウド同期(OneDrive 連携や Windows Backup 機能)を通じて初めて無償の選択肢が提供されるという仕組みでした。これは単なるセキュリティ更新を超えて、Microsoft のサービス利用を実質的に強制するものだとして批判を呼びました。
特に EU では、この条件が デジタル市場法(DMA) に違反する可能性が強調されました。DMA 第 6 条(6) では、ゲートキーパー企業が自社サービスを不当に優遇することを禁止しています。セキュリティ更新のような必須の機能を自社サービス利用と結びつけることは、まさにこの規定に抵触するのではないかという疑問が投げかけられました。加えて、デジタルコンテンツ指令(DCD) においても、消費者が合理的に期待できる製品寿命や更新提供義務との整合性が問われました。
こうした法的・社会的な背景の中で、消費者団体や規制当局からの圧力が強まり、Microsoft が方針を修正せざるを得なくなったのが今回の経緯です。
EUにおける展開
EU 域内では、消費者団体や規制当局からの強い圧力を受け、Microsoft は方針を大きく修正しました。当初の「Microsoft アカウント必須」「Microsoft Rewards 参加」などの条件は撤廃され、EEA(欧州経済領域)の一般消費者に対して、無条件で 1 年間の Extended Security Updates(ESU)を無料提供することを約束しました。これにより、利用者は 2026 年 10 月 13 日まで追加費用やアカウント登録なしにセキュリティ更新を受けられることになります。
Euroconsumers に宛てた Microsoft の回答を受けて、同団体は次のように評価しています。
“We are pleased to learn that Microsoft will provide a no-cost Extended Security Updates (ESU) option for Windows 10 consumer users in the European Economic Area (EEA). We are also glad this option will not require users to back up settings, apps, or credentials, or use Microsoft Rewards.”
つまり、今回の修正によって、EU 域内ユーザーはセキュリティを確保するために余計なサービス利用を強いられることなく、従来どおりの環境を維持できるようになったのです。これは DMA(デジタル市場法)の趣旨に合致するものであり、EU の規制が実際にグローバル企業の戦略を修正させた具体例と言えるでしょう。
一方で、Euroconsumers は Microsoft の対応を部分的な譲歩にすぎないと批判しています。
“The ESU program is limited to one year, leaving devices that remain fully functional exposed to risk after October 13, 2026. Such a short-term measure falls short of what consumers can reasonably expect…”
この指摘の背景には、Windows 10 を搭載する数億台規模のデバイスが依然として市場に残っている現実があります。その中には、2017 年以前に発売された古い PC で Windows 11 にアップグレードできないものが多数含まれています。これらのデバイスは十分に稼働可能であるにもかかわらず、1 年後にはセキュリティ更新が途絶える可能性が高いのです。
さらに、Euroconsumers は 持続可能性と電子廃棄物削減 の観点からも懸念を表明しています。
“Security updates are critical for the viability of refurbished and second-hand devices, which rely on continued support to remain usable and safe. Ending updates for functional Windows 10 systems accelerates electronic waste and undermines EU objectives on durable, sustainable digital products.”
つまり、セキュリティ更新を短期で打ち切ることは、まだ使える端末を廃棄に追いやり、EU が掲げる「循環型消費」や「持続可能なデジタル製品」政策に逆行するものだという主張です。
今回の合意により、少なくとも 2026 年 10 月までは EU の消費者が保護されることになりましたが、その後の対応は依然として不透明です。Euroconsumers は Microsoft に対し、さらなる延長や恒久的な解決策を求める姿勢を示しており、今後 1 年間の交渉が次の焦点となります。
EU域外の対応と反応
EU 域外のユーザーが ESU を利用するには、依然として以下の条件が課されています。
- Microsoft アカウント必須
- クラウド同期(OneDrive や Windows Backup)を通じた利用登録
- 年額約 30 ドル(または各国通貨換算)での課金
Tom’s Hardware は次のように報じています。
“Windows 10 Extended Support is now free, but only in Europe — Microsoft capitulates on controversial $30 ESU price tag, which remains firmly in place for the U.S.”
つまり、米国を中心とする EU 域外のユーザーは、EU のように「無条件・無償」の恩恵を受けられず、依然として追加費用を支払う必要があるという状況です。
不満と批判の声
こうした地域差に対して、各国メディアやユーザーからは批判が相次いでいます。TechRadar は次のように伝えています。
“Windows 10’s year of free updates now comes with no strings attached — but only some people will qualify.”
SNS やフォーラムでも「地理的差別」「不公平な二層構造」といった批判が見られます。特に米国や英国のユーザーからは「なぜ EU だけが特別扱いされるのか」という不満の声が強く上がっています。
また、Windows Latest は次のように指摘しています。
“No, you’ll still need a Microsoft account for Windows 10 ESU in Europe [outside the EU].”
つまり、EU を除く市場では引き続きアカウント連携が必須であり、プライバシーやユーザーの自由を損なうのではないかという懸念が残されています。
代替 OS への関心
一部のユーザーは、こうした対応に反発して Windows 以外の選択肢、特に Linux への移行を検討していると報じられています。Reddit や海外 IT コミュニティでは「Windows に縛られるよりも、Linux を使った方が自由度が高い」という議論が活発化しており、今回の措置が OS 移行のきっかけになる可能性も指摘されています。
報道の強調点
多くのメディアは一貫して「EU 限定」という点を強調しています。
- PC Gamer: “Turns out Microsoft will offer Windows 10 security updates for free until 2026 — but not in the US or UK.”
- Windows Central: “Microsoft makes Windows 10 Extended Security Updates free for an extra year — but only in certain markets.”
これらの記事はいずれも、「無条件無料は EU だけ」という事実を強調し、世界的なユーザーの間に不公平感を生んでいる現状を浮き彫りにしています。
考察
今回の一連の動きは、Microsoft の戦略と EU 規制の力関係を象徴的に示す事例となりました。従来、Microsoft のような巨大プラットフォーム企業は自社のエコシステムにユーザーを囲い込む形でサービスを展開してきました。しかし、EU ではデジタル市場法(DMA)やデジタルコンテンツ指令(DCD)といった法的枠組みを背景に、こうした企業慣行に実効的な制約がかけられています。今回「Microsoft アカウント不要・無条件での無料 ESU 提供」という譲歩が実現したのは、まさに規制当局と消費者団体の圧力が効果を発揮した例といえるでしょう。
一方で、この対応が EU 限定 にとどまったことは新たな問題を引き起こしました。米国や日本などのユーザーは依然として課金や条件付きでの利用を強いられており、「なぜ EU だけが特別扱いなのか」という不公平感が広がっています。国際的なサービスを提供する企業にとって、地域ごとの規制差がそのままサービス格差となることは、ブランドイメージや顧客信頼を損なうリスクにつながります。特にセキュリティ更新のような本質的に不可欠な機能に地域差を持ち込むことは、単なる「機能の差別化」を超えて、ユーザーの安全性に直接影響を与えるため、社会的反発を招きやすいのです。
さらに、今回の措置が 持続可能性 の観点から十分でないことも問題です。EU 域内でさえ、ESU 無償提供は 1 年間に限定されています。Euroconsumers が指摘するように、2026 年以降は再び数億台規模の Windows 10 デバイスが「セキュリティ更新なし」という状況に直面する可能性があります。これはリファービッシュ市場や中古 PC の活用を阻害し、電子廃棄物の増加を招くことから、EU が推進する「循環型消費」と真っ向から矛盾します。Microsoft にとっては、サポート延長を打ち切ることで Windows 11 への移行を促進したい意図があると考えられますが、その裏で「使える端末が強制的に廃棄に追い込まれる」構造が生まれてしまいます。
また、今回の事例は「ソフトウェアの寿命がハードウェアの寿命を強制的に決める」ことの危うさを改めて浮き彫りにしました。ユーザーが日常的に利用する PC がまだ十分に稼働するにもかかわらず、セキュリティ更新の停止によって利用継続が事実上困難になる。これは単なる技術的問題ではなく、消費者の信頼、環境政策、さらには社会全体のデジタル基盤に関わる大きな課題です。
今後のシナリオとしては、次のような可能性が考えられます。
- Microsoft が EU との協議を重ね、ESU の延長をさらに拡大する → EU 法制との整合性を図りつつ、消費者保護とサステナビリティを両立させる方向。
- 他地域でも政治的・消費者的圧力が強まり、EU と同等の措置が拡大する → 米国や日本で消費者団体が動けば、同様の譲歩を引き出せる可能性。
- Microsoft が方針を変えず、地域間格差が固定化する → その場合、Linux など代替 OS への移行が加速し、長期的に Microsoft の支配力が揺らぐリスクも。
いずれにしても、今回の一件は「セキュリティ更新はユーザーにとって交渉余地のあるオプションではなく、製品寿命を左右する公共性の高い要素」であることを示しました。Microsoft がこの問題をどのように処理するのかは、単なる一製品の延命措置を超えて、グローバルなデジタル社会における責任のあり方を問う試金石になるでしょう。
おわりに
今回の Windows 10 Extended Security Updates(ESU)をめぐる一連の動きは、単なるサポート延長措置にとどまらず、グローバル企業と地域規制の力関係、そして消費者保護と持続可能性をめぐる大きなテーマを浮き彫りにしました。
まず、EU 域内では、消費者団体と規制当局の働きかけにより、Microsoft が「無条件・無償」という形で譲歩を余儀なくされました。セキュリティ更新のような不可欠な機能を自社サービス利用と結びつけることは DMA に抵触する可能性があるという論点が、企業戦略を修正させる決定的な要因となりました。これは、規制が実際に消費者に利益をもたらすことを証明する事例と言えます。
一方で、EU 域外の状況は依然として厳しいままです。米国や日本を含む地域では、Microsoft アカウントの利用が必須であり、年額課金モデルも継続しています。EU とその他地域との間に生じた「セキュリティ更新の地域格差」は、ユーザーにとって大きな不公平感を生み出しており、国際的な批判の火種となっています。セキュリティという本質的に公共性の高い要素が地域によって異なる扱いを受けることは、今後も議論を呼ぶでしょう。
さらに、持続可能性の課題も解決されていません。今回の EU 向け措置は 1 年間に限定されており、2026 年 10 月以降の数億台規模の Windows 10 デバイスの行方は依然として不透明です。セキュリティ更新の打ち切りはリファービッシュ市場や中古 PC の寿命を縮め、結果として電子廃棄物の増加につながります。これは EU の「循環型消費」や「持続可能なデジタル製品」という政策目標とも矛盾するため、さらなる延長や新たな仕組みを求める声が今後高まる可能性があります。
今回の件は、Microsoft の戦略、規制当局の影響力、消費者団体の役割が交差する非常に興味深い事例です。そして何より重要なのは、セキュリティ更新は単なるオプションではなく、ユーザーの権利に直結する問題だという認識を社会全体で共有する必要があるという点です。
読者として注視すべきポイントは三つあります。
- Microsoft が 2026 年以降にどのような対応を打ち出すか。
- EU 以外の地域で、同様の規制圧力や消費者運動が展開されるか。
- 企業のサポートポリシーが、環境・社会・規制とどのように折り合いをつけるか。
Windows 10 ESU の行方は、単なる OS サポート延長の問題を超え、グローバルなデジタル社会における企業責任と消費者権利のバランスを象徴する事例として、今後も注視していく必要があるでしょう。
参考文献
- Microsoft lets Windows 10 users get one more year of updates without Microsoft account
https://www.neowin.net/news/microsoft-lets-windows-10-users-get-one-more-year-of-updates-without-microsoft-account/ - Major backtrack as Microsoft makes Windows 10 Extended Security Updates free for an extra year — but only in certain markets
https://www.windowscentral.com/microsoft/windows-10/major-backtrack-as-microsoft-makes-windows-10-extended-security-updates-free-for-an-extra-year-but-only-in-certain-markets - Windows 10 Extended Support is now free, but only in Europe — Microsoft capitulates on controversial $30 ESU price tag, which remains firmly in place for the U.S.
https://www.tomshardware.com/software/windows/windows-10-extended-support-is-now-free-but-only-in-europe-microsoft-capitulates-on-controversial-usd30-esu-price-tag-which-remains-firmly-in-place-for-the-u-s - Windows 10’s year of free updates now comes with no strings attached — but only some people will qualify
https://www.techradar.com/computing/windows/windows-10s-year-of-free-updates-now-comes-with-no-strings-attached-but-only-some-people-will-qualify - Turns out Microsoft will offer Windows 10 security updates for free until 2026 — but not in the US or UK
https://www.pcgamer.com/software/operating-systems/turns-out-microsoft-will-offer-windows-10-security-updates-for-free-until-2026-but-not-in-the-us-or-uk - No, you’ll still need a Microsoft account for Windows 10 ESU in Europe
https://www.windowslatest.com/2025/09/26/no-youll-still-need-a-microsoft-account-for-windows-10-esu-in-europe/ - Response to Microsoft’s Letter – Windows 10 end-of-support policy and Alleged Non-Compliance with EU Law (Directive (EU) 2019/770 and Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Markets Act))
https://www.euroconsumers.org/wp-content/uploads/2025/09/Euroconsumers_vs_Microsoft_092025.pdf