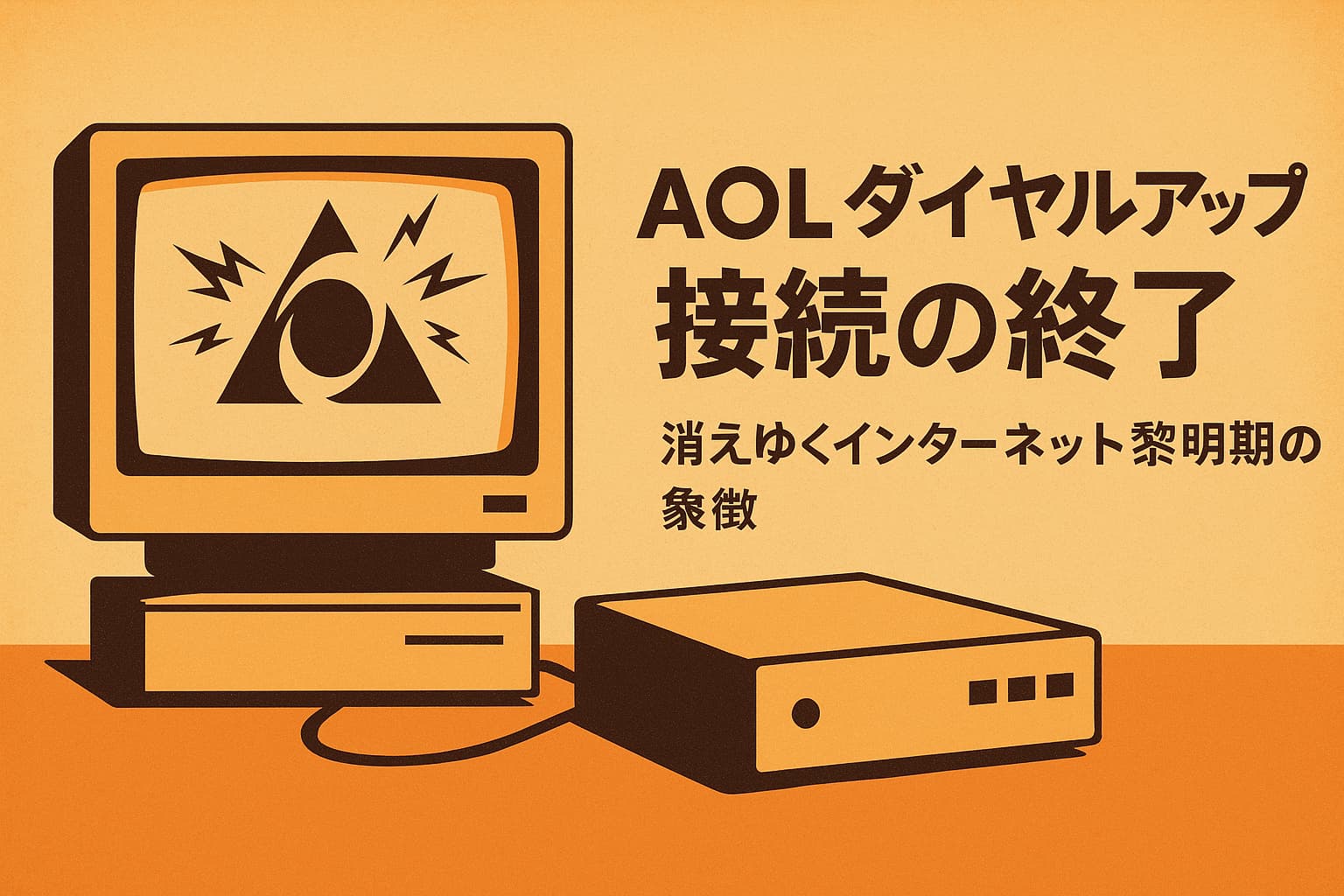2025年9月末をもって、AOLがダイヤルアップ接続サービスを正式に終了します。
「You’ve got mail!」のフレーズとともに多くのユーザーの記憶に残るこのサービスは、1990年代から2000年代初頭にかけて、世界中の人々にインターネットの扉を開いた象徴的な存在でした。パソコンを起動し、モデムのケーブルを電話線に差し込み、あの「ピー・ヒョロロ…ガーッ」という独特の接続音を聞きながら、少しずつウェブページが表示されていく──そんな体験は、世代によっては懐かしい日常の一部だったのです。
ブロードバンドや光回線、さらには5Gや衛星通信が普及した現在からすれば、ダイヤルアップは速度も利便性も桁違いに劣る古い技術です。それでも、2020年代半ばになってもなお、米国や日本では「最後の利用者層」のためにダイヤルアップサービスが細々と維持されてきました。なぜこれほど長く残ってきたのか、その背景にはインフラ格差やレガシーシステムの存在など、単なる技術的進化では語りきれない事情があります。
この記事では、AOLのサービス終了をきっかけに、米国と日本におけるダイヤルアップの現状やサポート状況を振り返りながら、なぜこの接続方式が維持されてきたのかを考えていきます。
米国における現状
米国では、かつて数千万人がAOLのダイヤルアップを通じて初めて「インターネット」という世界に足を踏み入れました。まだYouTubeもSNSも存在せず、ウェブページは文字とシンプルな画像が中心。メールチェックやチャットルームへの参加が、オンラインで過ごす主要な時間の使い方でした。テレビCMやCD-ROMで大量に配布されたインストーラーディスクは、インターネットの入口を象徴するアイテムでもあり、「家に帰ったらとりあえずAOLを立ち上げる」という習慣は、90年代のアメリカ家庭に広く浸透していました。
その後、ブロードバンドが普及し、ダイヤルアップは「遅い」「不便」という理由から次第に姿を消していきましたが、それでも完全にはなくならなかったのです。2020年代に入っても、米国の地方部や山間部など、ブロードバンド回線が十分に整備されていない地域では、ダイヤルアップが最後の手段として残っていました。2023年の調査では、なお16万世帯以上が利用していたと報告されており、驚きを持って受け止められました。
AOLがダイヤルアップを提供し続けた背景には、単なる通信インフラの問題だけでなく、「インターネット黎明期の象徴」を守り続ける意味合いもあったでしょう。あの接続音を聞きながらブラウザが一行ずつ文字を描画していく体験は、インターネットという技術が「未知の世界への入り口」だった時代の記憶そのものです。たとえ数は減っても、その体験に依存する人々や地域が存在する限り、AOLは“最後の砦”としてサービスを継続していたのです。
今回のサービス終了は、そうした“残された最後のユーザー層”にとっても、大きな区切りとなります。懐かしさと同時に、ついに消えゆく文化への寂しさが漂う瞬間だといえるでしょう。
日本における現状
日本でも1990年代後半から2000年代初頭にかけて、ダイヤルアップ接続はインターネットの入り口でした。当時は「テレホーダイ」や「テレホーダイタイム(深夜・早朝の定額時間帯)」といった電話料金の仕組みと組み合わせて利用するのが一般的で、多くの学生や社会人が夜中になると一斉に回線をつなぎ、チャットや掲示板、初期のホームページ巡りを楽しんでいました。家族に「電話を使いたいから切って!」と怒られたり、通信中に電話がかかってきて接続が途切れたり──そうしたエピソードは、当時インターネットに触れた人々にとって懐かしい思い出でしょう。
その後、日本はブロードバンドの普及で世界をリードする国となりました。2000年代初頭からADSLが急速に広がり、さらに光回線が政府の政策と通信事業者の競争によって全国に整備されていきました。その結果、ダイヤルアップは急速に過去のものとなり、2000年代半ばにはほとんどの家庭がブロードバンドに移行しました。
それでも、サービス自体は完全に消え去ったわけではありません。たとえばASAHIネットは2028年までダイヤルアップ接続を維持する方針を公表しており、象徴的な「最後のサービス」として細々と提供が続いています。ただし、利用者数は統計に現れるほどの規模ではなく、もはや実用というよりも、過去からの継続利用や特定のレガシー環境のための“延命措置”に近い存在です。
つまり、日本におけるダイヤルアップの現状は「ほぼ歴史的な名残」に過ぎません。しかし、その存在はかつてのインターネット文化を思い出させるきっかけにもなります。掲示板文化の隆盛や、夜更かししてのチャット、モデムの甲高い接続音──そうした体験を通じて、多くの人が初めて「世界とつながる」感覚を味わいました。今や高速回線が当たり前となった日本においても、ダイヤルアップは“原風景”として静かに残り続けているのです。
なぜ維持されてきたのか?
ダイヤルアップ接続がここまで長く生き延びてきた理由は、単なる「技術の遅れ」だけではありません。その背景には、人々の生活やインフラ事情、そして文化的な側面が深く関わっています。
まず大きな要因は 地方や山間部のインフラ不足 です。米国では広大な国土のため、都市部では高速インターネットが整備されても、農村部や山間部ではブロードバンドの敷設が遅れました。その結果、電話回線しか選択肢がない家庭にとって、ダイヤルアップは“最後の命綱”だったのです。日本でも、光回線が全国に普及するまでの間は、過疎地域で細々と使われ続けていました。
次に挙げられるのは、コストと使い慣れた安心感 です。ダイヤルアップは特別な工事や高額な初期投資を必要とせず、既存の電話回線とモデムがあればすぐに始められました。特に高齢者や「新しいものに不安を感じる」ユーザーにとって、環境を変えずに継続できるのは大きな安心材料でした。あの接続音を聞くと「ちゃんとつながっている」と実感できた、という声もあったほどです。
さらに、レガシーシステムへの依存 も無視できません。企業や自治体の中には、古いシステムや機器がダイヤルアップを前提に作られていた例があり、移行コストや互換性の問題から完全に手放すことが難しい場合がありました。セキュリティや速度面では見劣りしても、「確実に使えるから残しておく」――そんな現実的な判断もあったのです。
そして最後に、文化的・象徴的な意味合い もありました。特にAOLのようなブランドにとって、ダイヤルアップは単なるサービスではなく「会社のアイデンティティの一部」でした。あの接続音や「You’ve got mail!」という通知は、インターネットの黎明期を体験した人々にとって、いわば青春の音。企業にとってもユーザーにとっても、それを失うことはひとつの時代が終わることを意味していたのです。
結局のところ、ダイヤルアップが維持されてきたのは「利便性ではなく必要性」、そして「効率性ではなく思い出」でした。速度も利便性もすでに過去のものとなりながら、なお生き延びてきたのは、生活の事情と人々の記憶が支えてきたからだといえるでしょう。
終わりゆく「接続音」の時代
ダイヤルアップ接続といえば、やはり忘れられないのが「ピーヒョロロ…ガーッ」という接続音です。モデム同士が電話回線を通じて交渉を始めるこの音は、当時インターネットに触れていた人にとって特別な意味を持つものでした。まるで「これから新しい世界につながるよ」と知らせる合図のように響き、儀式めいた高揚感を伴っていたのです。
接続に成功すると、ブラウザにはゆっくりとページが描画されていきました。文字が一行ずつ現れ、画像が少しずつ表示されていく。待ち時間は決して短くはありませんでしたが、その分「何が出てくるのだろう」という期待感が膨らみ、ページが完成するまでの過程そのものがワクワクに満ちていました。いまの高速インターネットでは味わえない「待つ楽しみ」が、あの時代には確かに存在していたのです。
また、この接続音は家庭内の風景にも深く刻まれています。インターネットを使っている間は電話が話中になるため、家族から「電話がつながらない!」と叱られるのは日常茶飯事。ときには親から「もう夜遅いんだから切りなさい」と言われ、しぶしぶ接続を終えることもありました。一方で、夜11時を過ぎると始まる「テレホーダイ」タイムに合わせて、全国の学生や社会人が一斉にログインし、掲示板やチャットが深夜まで賑わった光景も忘れられません。接続音が鳴り響いた瞬間、誰もが同じように「今、つながった!」と感じていたのです。
さらに、ダイヤルアップの接続音は「失敗」と隣り合わせでもありました。最後まで音が続いたのに、なぜかつながらず再挑戦を余儀なくされることもしばしば。何度も「ピーヒョロロ…ガーッ」を繰り返し聞きながら、「今度こそ頼む!」と祈るような気持ちで接続を待った経験は、多くの人が共有している懐かしいエピソードでしょう。
こうした記憶の積み重ねが、「ピーヒョロロ…ガーッ」を単なる通信音以上の存在にしました。それはインターネット黎明期のシンボルであり、当時のユーザーにとっての青春の一部だったのです。AOLのダイヤルアップ終了は、この音がついに公式に“現役を退く”ことを意味します。日常で耳にすることはなくなりますが、あの音を知る世代にとっては、一生忘れることのできない「インターネットの原風景」として心に刻まれ続けるでしょう。
おわりに
AOLのダイヤルアップ終了は、単なるサービス終了のニュースではありません。それは「インターネット黎明期の記憶」に区切りをつける出来事であり、技術の進化とともに文化の一部が静かに幕を下ろす瞬間でもあります。
米国では、なお十数万世帯が「最後の命綱」としてダイヤルアップを利用していました。日本でも、光回線が全国に普及した後も、ASAHIネットのようにサービスを維持してきた事業者がありました。どちらの国においても、もはや主流の技術ではなく、実用性はほとんど失われていましたが、それでも「使い続ける人がいる限り」提供をやめることはできなかったのです。そこには、単なる顧客対応以上に「人々の生活や文化を支える」というサービス提供者としての矜持も感じられます。
あの「ピーヒョロロ…ガーッ」という接続音は、遅さや不便さを象徴するものでありながらも、多くの人にとっては「初めて世界とつながった瞬間の音」でした。夜中にこっそり接続して掲示板をのぞいたこと、画像が表示されるのをワクワクしながら待ったこと、電話回線を占有して家族に怒られたこと──そうした小さな思い出の断片が積み重なって、私たちの“インターネット体験の原風景”を形作っていました。
いまや私たちは、スマートフォンを通じて24時間常時接続され、動画も音楽も瞬時に楽しめる時代を生きています。その便利さと引き換えに、かつての「接続する儀式」や「待つ時間のワクワク感」は失われました。だからこそ、ダイヤルアップの終焉は単なる技術的な進化ではなく、「一つの文化の終焉」として受け止める価値があるのではないでしょうか。
AOLの終了は、過去を懐かしむだけでなく、これからのインターネットがどこへ向かうのかを考える契機にもなります。高速化と利便性の中で失ったもの、あるいは新たに獲得したもの。その両方を見つめ直しながら、私たちは次の世代の「インターネットの音」を刻んでいくのだと思います。
参考文献
- AOL is finally shutting down its dial-up internet service(AP News)
https://apnews.com/article/275a81f8a725619663437350b7c7ed36 - End is near for the landline-based service that got America online in the ’90s(Washington Post)
https://www.washingtonpost.com/nation/2025/08/11/aol-america-online-dial-up - End of an era: AOL to discontinue its dial-up internet service after 30 years(The Guardian)
https://www.theguardian.com/us-news/2025/aug/11/aol-dial-up-internet - You had mail: AOL finally discontinues dial-up internet service(Apple Insider)
https://appleinsider.com/articles/25/08/09/you-had-mail-aol-finally-discontinues-dial-up-internet-service - AOL to end dial-up service in 2025, affecting 175,000 rural users(WebProNews)
https://www.webpronews.com/aol-to-end-dial-up-service-in-2025-affecting-175000-rural-users - AOL discontinues its dial-up internet — and we’re just surprised they even offered it in 2025(PC Gamer)
https://www.pcgamer.com/gaming-industry/aol-discontinues-its-dial-up-internet-and-were-just-surprised-they-even-offered-it-in-2025 - AOL(Wikipedia)
https://en.wikipedia.org/wiki/AOL - Internet in Japan(Wikipedia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_in_Japan - ASAHIネット「ダイヤルアップ接続サービス提供終了延期のお知らせ」
https://asahi-net.jp/news/20230614_01.html