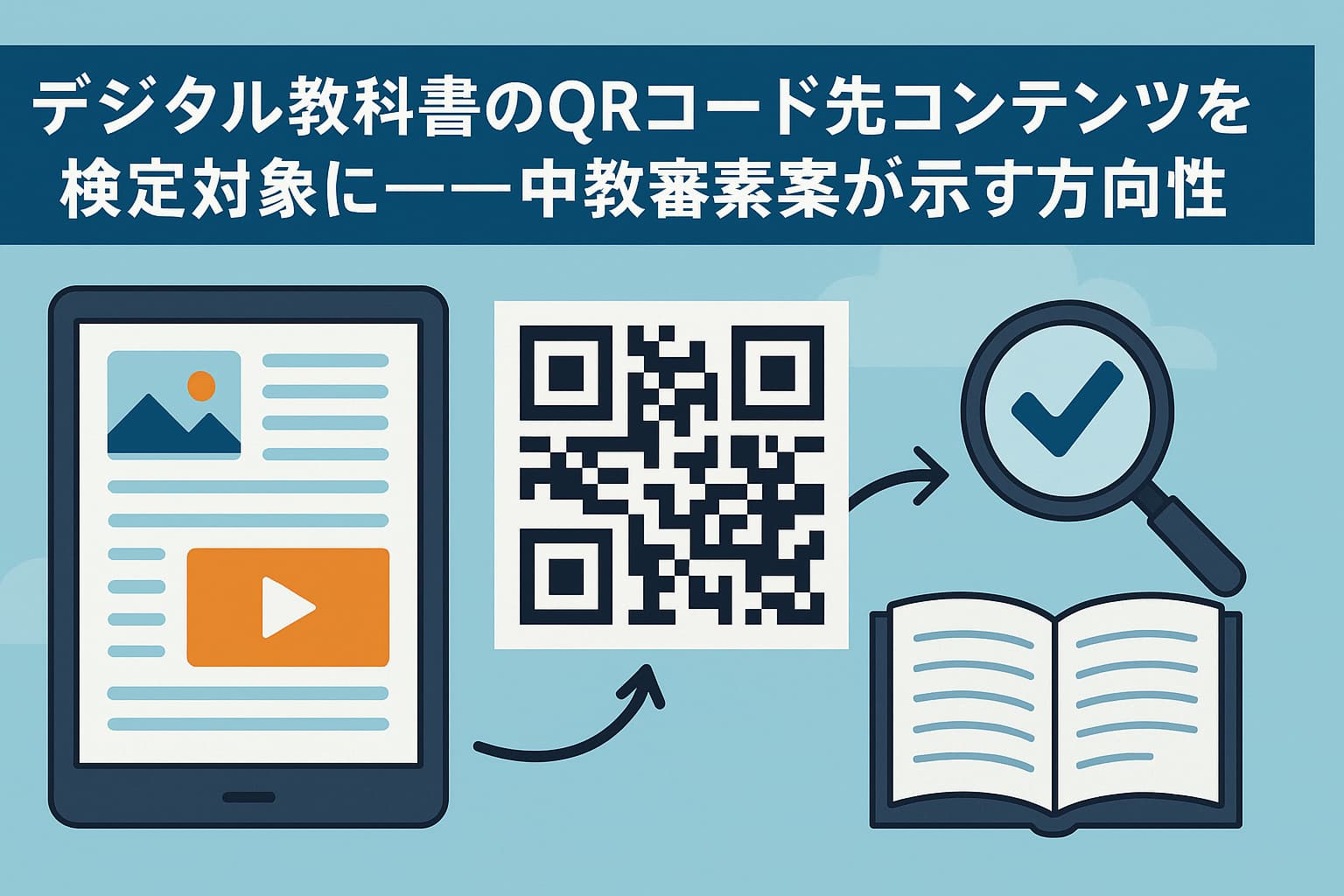近年、生成AIは文章生成や画像生成などの分野で目覚ましい進化を遂げ、日常生活からビジネス、教育、研究に至るまで幅広く活用されるようになってきました。その一方で、AIの性能を支える基盤である「学習データ」をどのように収集し、利用するのかという問題が世界的な議論を呼んでいます。特に、著作権で保護された書籍や記事、画像などを権利者の許可なく利用することは、創作者の権利侵害につながるとして、深刻な社会問題となりつつあります。
この数年、AI企業はモデルの性能向上のために膨大なデータを必要としてきました。しかし、正規に出版されている紙の書籍や電子書籍は、DRM(デジタル著作権管理)やフォーマットの制限があるため、そのままでは大量処理に適さないケースが多く見られます。その結果、海賊版データや「シャドウライブラリ」と呼ばれる違法コピー集が、AI訓練のために利用されてきた疑いが強く指摘されてきました。これは利便性とコストの面から選ばれやすい一方で、著作者に対する正当な補償を欠き、著作権侵害として訴訟につながっています。
2025年9月には、この問題を象徴する二つの大きな出来事が立て続けに報じられました。一つは、Appleが自社AIモデル「OpenELM」の訓練に書籍を無断使用したとして作家から訴えられた件。もう一つは、Anthropicが著者集団との間で1.5億ドル規模の和解に合意した件です。前者は新たな訴訟の端緒となり、後者はAI企業による著作権関連で史上最大級の和解とされています。
これらの事例は、単に一企業や一分野の問題にとどまりません。AI技術が社会に定着していく中で、創作者の権利をどのように守りつつ、AI産業の健全な発展を両立させるのかという、普遍的かつ国際的な課題を突きつけています。本記事では、AppleとAnthropicを中心とした最新動向を紹介するとともに、他企業の事例、権利者とAI企業双方の主張、そして今後の展望について整理し、AI時代の著作権問題を多角的に考察していきます。
Appleに対する訴訟
2025年9月5日、作家のGrady Hendrix氏(ホラー小説家として知られる)とJennifer Roberson氏(ファンタジー作品の著者)は、Appleを相手取りカリフォルニア州で訴訟を起こしました。訴状によれば、Appleが発表した独自の大規模言語モデル「OpenELM」の学習過程において、著者の書籍が無断でコピーされ、権利者に対する許可や補償が一切ないまま使用されたと主張されています。
問題の焦点は、Appleが利用したとされる学習用データの出所にあります。原告側は、著作権で保護された書籍が海賊版サイトや「シャドウライブラリ」と呼ばれる違法コピー集を通じて収集された可能性を指摘しており、これは権利者に対する重大な侵害であるとしています。これにより、Appleが本来であれば市場で正規購入し、ライセンスを結んだ上で利用すべき作品を、無断で自社AIの訓練に転用したと訴えています。
この訴訟は、Appleにとって初めての本格的なAI関連の著作権侵害訴訟であり、業界にとっても象徴的な意味を持ちます。これまでの類似訴訟は主にスタートアップやAI専業企業(Anthropic、Stability AIなど)が対象でしたが、Appleのような大手テクノロジー企業が名指しされたことは、AI訓練を巡る著作権問題がもはや一部企業だけのリスクではないことを示しています。
現時点でApple側は公式なコメントを控えており、原告側代理人も具体的な補償額や和解条件については明言していません。ただし、提訴を主導した著者らは「AIモデルの開発に作品を使うこと自体を全面的に否定しているわけではなく、正当なライセンスと補償が必要だ」との立場を示しています。この点は、他の訴訟で見られる著者団体(Authors Guildなど)の主張とも一致しています。
このApple訴訟は、今後の法廷闘争により、AI企業がどのように学習データを調達すべきかについて新たな基準を生み出す可能性があります。特に、正規の電子書籍や紙媒体がAI学習に適さない形式で流通している現状において、出版社や著者がAI向けにどのような形でデータを提供していくのか、業界全体に課題を突きつける事例といえるでしょう。
Anthropicによる和解
2025年9月5日、AIスタートアップのAnthropicは、著者らによる集団訴訟に対して総額15億ドル(約2,200億円)を支払うことで和解に合意したと報じられました。対象となったのは約50万冊に及ぶ書籍で、計算上は1冊あたりおよそ3,000ドルが著者へ分配される見込みです。この規模は、AI企業に対する著作権訴訟として過去最大級であり、「AI時代における著作権回収」の象徴とされています。
訴訟の発端は、作家のAndrea Bartz氏、Charles Graeber氏、Kirk Wallace Johnson氏らが中心となり、Anthropicの大規模言語モデル「Claude」が無断コピーされた書籍を用いて訓練されたと主張したことにあります。裁判では、Anthropicが海賊版サイト経由で収集された数百万冊にのぼる書籍データを中央リポジトリに保存していたと指摘されました。裁判官のWilliam Alsup氏は2025年6月の審理で「AI訓練に著作物を使用する行為はフェアユースに該当する場合もある」としながらも、海賊版由来のデータを意図的に保存・利用した点は不正利用(著作権侵害)にあたると判断しています。
和解の条件には、金銭的補償に加えて、問題となったコピー書籍のデータ破棄が含まれています。これにより、訓練データとしての利用が継続されることを防ぎ、著者側にとっては侵害の再発防止措置となりました。一方、Anthropicは和解に応じたものの、著作権侵害を公式に認める立場は取っていません。今回の合意は、12月に予定されていた損害賠償審理を回避する狙いがあると見られています。
この和解は、AI企業が著作権リスクを回避するために積極的に妥協を選ぶ姿勢を示した点で注目されます。従来、AI企業の多くはフェアユースを盾に争う構えを見せていましたが、Anthropicは法廷闘争を続けるよりも、巨額の和解金を支払い早期決着を図る道を選びました。これは他のAI企業にとっても前例となり、今後の対応方針に影響を与える可能性があります。
また、この和解は権利者側にとっても大きな意味を持ちます。単なる補償金の獲得にとどまらず、AI企業に対して「正規のライセンスを通じてのみ学習利用を行うべき」という強いメッセージを発信する結果となったからです。訴訟を担当した弁護士Justin Nelson氏も「これはAI時代における著作権を守るための歴史的な一歩だ」と述べており、出版業界やクリエイター団体からも歓迎の声が上がっています。
Apple・Anthropic以外の類似事例
AppleやAnthropicの事例は大きな注目を集めましたが、著作権を巡る問題はそれらに限られません。生成AIの分野では、他の主要企業やスタートアップも同様に訴訟や和解に直面しており、対象となる著作物も書籍だけでなく記事、法律文書、画像、映像作品へと広がっています。以下では、代表的な企業ごとの事例を整理します。
Meta
Metaは大規模言語モデル「LLaMA」を公開したことで注目を集めましたが、その訓練データに無断で書籍が利用されたとする訴訟に直面しました。原告は、Metaが「LibGen」や「Anna’s Archive」といったいわゆる“シャドウライブラリ”から違法コピーされた書籍を利用したと主張しています。2025年6月、米国連邦裁判所の裁判官は、AI訓練への著作物利用について一部フェアユースを認めましたが、「状況によっては著作権侵害となる可能性が高い」と明言しました。この判断は、AI訓練に関するフェアユースの適用範囲に一定の指針を与えたものの、グレーゾーンの広さを改めて浮き彫りにしています。
OpenAI / Microsoft と新聞社
OpenAIとMicrosoftは、ChatGPTやCopilotの開発・運営を通じて新聞社や出版社から複数の訴訟を受けています。特に注目されたのは、米国の有力紙「New York Times」が2023年末に提訴したケースです。Timesは、自社の記事が許可なく学習データとして利用されただけでなく、ChatGPTの出力が元の記事に酷似していることを問題視しました。その後、Tribune Publishingや他の報道機関も同様の訴訟を提起し、2025年春にはニューヨーク南部地区連邦裁判所で訴訟が統合されました。現在も審理が続いており、報道コンテンツの利用を巡る基準づくりに大きな影響を与えると見られています。
Ross Intelligence と Thomson Reuters
法律系AIスタートアップのRoss Intelligenceは、法情報サービス大手のThomson Reutersから著作権侵害で提訴されました。問題となったのは、同社が「Westlaw」に掲載された判例要約を無断で利用した点です。Ross側は「要約はアイデアや事実にすぎず、著作権保護の対象外」と反論しましたが、2025年2月に連邦裁判所は「要約は独自の表現であり、著作権保護に値する」との判断を下しました。この判決は、AI訓練に利用される素材がどこまで保護対象となるかを示す先例として、法務分野だけでなく広範な業界に波及効果を持つと考えられています。
Stability AI / Midjourney / Getty Images
画像生成AIを巡っても、著作権侵害を理由とした複数の訴訟が進行しています。Stability AIとMidjourneyは、アーティストらから「作品を無断で収集・利用し、AIモデルの学習に用いた」として訴えられています。原告は、AIが生成する画像が既存作品のスタイルや構図を模倣している点を指摘し、権利者の市場価値を損なうと主張しています。さらに、Getty Imagesは2023年にStability AIを相手取り提訴し、自社の画像が許可なく学習データに組み込まれたとしています。特に問題視されたのは、Stable Diffusionの出力にGettyの透かしが残っていた事例であり、違法利用の証拠とされました。これらの訴訟は現在も審理中で、ビジュアルアート分野におけるAIと著作権の境界を定める重要な試金石と位置づけられています。
Midjourney と大手メディア企業
2025年6月には、DisneyやNBCUniversalといった大手エンターテインメント企業がMidjourneyを提訴しました。訴状では、自社が保有する映画やテレビ作品のビジュアル素材が無断で収集され、学習データとして使用された疑いがあるとされています。メディア大手が直接AI企業を訴えたケースとして注目され、判決次第では映像コンテンツの利用に関する厳格なルールが確立される可能性があります。
こうした事例は、AI企業が学習データをどのように調達すべきか、またどの範囲でフェアユースが適用されるのかを巡る法的・倫理的課題を鮮明にしています。AppleやAnthropicの事例とあわせて見ることで、AIと著作権を巡る問題が業界全体に広がっていることが理解できます。
権利者側の主張
権利者側の立場は一貫しています。彼らが問題視しているのは、AIによる利用そのものではなく、無断利用とそれに伴う補償の欠如です。多くの著者や出版社は、「AIが作品を学習に用いること自体は全面的に否定しないが、事前の許諾と正当な対価が必要だ」と主張しています。
Anthropicの訴訟においても、原告のAndrea Bartz氏やCharles Graeber氏らは「著者の作品は市場で公正な価格で購入できるにもかかわらず、海賊版経由で無断利用された」と強く批判しました。弁護士のJustin Nelson氏は、和解後に「これはAI時代における著作権を守るための史上最大級の回収だ」とコメントし、単なる金銭補償にとどまらず、業界全体に向けた抑止力を意識していることを示しました。
また、米国の著者団体 Authors Guild も繰り返し声明を発表し、「AI企業は著作権者を尊重し、利用の透明性を確保したうえでライセンス契約を結ぶべきだ」と訴えています。特に、出版契約の中にAI利用権が含まれるのか否かは曖昧であり、著者と出版社の間でトラブルの種になる可能性があるため、独立した権利として明示すべきだと強調しています。
こうした声は欧米に限られません。フランスの新聞社 Le Monde では、AI企業との契約で得た収益の25%を記者に直接分配する仕組みを導入しました。これは、単に企業や出版社が利益を得るだけでなく、実際にコンテンツを創作した人々へ補償を行き渡らせるべきだという考え方の表れです。英国では、著作権管理団体CLAがAI訓練用の集団ライセンス制度を準備しており、権利者全体に正当な収益を還元する仕組みづくりが進められています。
さらに、権利者たちは「違法コピーの破棄」も強く求めています。Anthropicの和解に盛り込まれたコピー書籍データの削除は、その象徴的な措置です。権利者にとって、補償を受けることと同じくらい重要なのは、自分の著作物が今後も無断で利用され続けることを防ぐ点だからです。
総じて、権利者側が求めているのは次の三点に整理できます。
- 公正な補償 ― AI利用に際して正当なライセンス料を支払うこと。
- 透明性 ― どの作品がどのように利用されたのかを明らかにすること。
- 抑止力 ― 無断利用が繰り返されないよう、違法コピーを破棄し、制度面でも規制を整備すること。
これらの主張は、単なる対立ではなく、創作者の権利を守りつつAI産業の発展を持続可能にするための条件として提示されています。
AI企業側の立場
AI企業の多くは、著作権侵害の主張に対して「フェアユース(公正利用)」を強調し、防衛の柱としています。特に米国では、著作物の一部利用が「教育的・研究的・非営利的な目的」に該当すればフェアユースが認められることがあり、AI訓練データがその範囲に含まれるかどうかが激しく争われています。
Metaの対応
Metaは、大規模言語モデル「LLaMA」に関して著者から訴えられた際、訓練データとしての利用は「新たな技術的用途」であり、市場を直接侵害しないと主張しました。2025年6月、米連邦裁判所の裁判官は「AI訓練自体が直ちに著作権侵害に当たるわけではない」と述べ、Meta側に有利な部分的判断を下しました。ただし同時に、「利用の態様によっては侵害にあたる」とも指摘しており、全面的な勝訴とは言い切れない内容でした。Metaにとっては、AI業界にとって一定の防波堤を築いた一方で、今後のリスクを完全には払拭できなかった判決でした。
Anthropicの対応
AnthropicはMetaと対照的に、長期化する裁判闘争を避け、著者集団との和解を選びました。和解総額は15億ドルと巨額でしたが、無断利用を認める表現は回避しつつ、補償金とデータ破棄で早期決着を図りました。これは、投資家や顧客にとって法的リスクを抱え続けるよりも、巨額の和解を支払う方が企業価値の維持につながるとの判断が背景にあると考えられます。AI市場において信頼を維持する戦略的選択だったともいえるでしょう。
OpenAIとMicrosoftの対応
OpenAIとパートナーのMicrosoftは、新聞社や出版社からの訴訟に直面していますが、「フェアユースに該当する」との立場を堅持しています。加えて両社は、法廷闘争だけでなく、政策ロビー活動も積極的に展開しており、AI訓練データの利用を広範にフェアユースとして認める方向で米国議会や規制当局に働きかけています。さらに一部の出版社とは直接ライセンス契約を結ぶなど、対立と協調を並行して進める「二正面作戦」を採用しています。
業界全体の動向
AI企業全般に共通するのは、
- フェアユース論の強調 ― 法的防衛の基盤として主張。
- 和解や契約によるリスク回避 ― 裁判長期化を避けるための戦略。
- 透明性向上の試み ― 出力へのウォーターマーク付与やデータ利用の説明責任強化。
- 政策提言 ― 各国の政府や規制当局に働きかけ、法整備を有利に進めようとする動き。
といった複合的なアプローチです。
AI企業は著作権リスクを無視できない状況に追い込まれていますが、全面的に譲歩する姿勢も見せていません。今後の戦略は、「どこまでフェアユースで戦い、どこからライセンス契約で妥協するか」の線引きを探ることに集中していくと考えられます。
技術的背景 ― なぜ海賊版が選ばれたのか
AI企業が学習用データとして海賊版を利用した背景には、技術的・経済的な複数の要因があります。
1. 紙の書籍のデジタル化の困難さ
市場に流通する書籍の多くは紙媒体です。これをAIの学習用に利用するには、スキャンし、OCR(光学式文字認識)でテキスト化し、さらにノイズ除去や構造化といった前処理を施す必要があります。特に数百万冊単位の規模になると、こうした作業は膨大なコストと時間を要し、現実的ではありません。
2. 電子書籍のDRMとフォーマット制限
Kindleなどの商用電子書籍は、通常 DRM(デジタル著作権管理) によって保護されています。これにより、コピーや解析、機械学習への直接利用は制限されます。さらに、電子書籍のファイル形式(EPUB、MOBIなど)はそのままではAIの学習に適しておらず、テキスト抽出や正規化の工程が必要です。結果として、正規ルートでの電子書籍利用は技術的にも法的にも大きな障壁が存在します。
3. データ規模の要求
大規模言語モデルの訓練には、数千億から数兆トークン規模のテキストデータが必要です。こうしたデータを短期間に確保しようとすると、オープンアクセスの学術資料や公的文書だけでは不足します。出版社や著者と逐一契約して正規データを集めるのは非効率であり、AI企業はより「手っ取り早い」データ源を探すことになりました。
4. シャドウライブラリの利便性
LibGen、Z-Library、Anna’s Archiveなどの“シャドウライブラリ”は、何百万冊もの書籍を機械可読なPDFやEPUB形式で提供しており、AI企業にとっては極めて魅力的なデータ供給源でした。これらは検索可能で一括ダウンロードもしやすく、大規模データセットの構築に最適だったと指摘されています。実際、Anthropicの訴訟では、700万冊以上の書籍データが中央リポジトリに保存されていたことが裁判で明らかになりました。
5. 法的リスクの軽視
当初、AI業界では「学習に用いることはフェアユースにあたるのではないか」との期待があり、リスクが過小評価されていました。新興企業は特に、先行して大規模モデルを構築することを優先し、著作権問題を後回しにする傾向が見られました。しかし、実際には著者や出版社からの訴訟が相次ぎ、現在のように大規模な和解や損害賠償につながっています。
まとめ
つまり、AI企業が海賊版を利用した理由は「技術的に扱いやすく、コストがかからず、大規模データを即座に確保できる」という利便性にありました。ただし裁判所は「利便性は侵害を正当化しない」と明確に指摘しており、今後は正規ルートでのデータ供給体制の整備が不可欠とされています。出版社がAI学習に適した形式でのライセンス提供を進めているのも、この問題に対処するための動きの一つです。
出版社・報道機関の対応
AI企業による無断利用が大きな問題となる中、出版社や報道機関も独自の対応を進めています。その狙いは二つあります。ひとつは、自らの知的財産を守り、正当な対価を確保すること。もうひとつは、AI時代における持続可能なビジネスモデルを構築することです。
米国の動向
米国では、複数の大手メディアがすでにAI企業とのライセンス契約を結んでいます。
- New York Times は、Amazonと年間2,000万〜2,500万ドル規模の契約を締結し、記事をAlexaなどに活用できるよう提供しています。これにより、AI企業が正規ルートで高品質なデータを利用できる仕組みが整いました。
- Thomson Reuters も、AI企業に記事や法律関連コンテンツを提供する方向性を打ち出しており、「ライセンス契約は良質なジャーナリズムを守ると同時に、収益化の新たな柱になる」と明言しています。
- Financial Times や Washington Post もOpenAIなどと交渉を進めており、報道コンテンツが生成AIの重要な訓練材料となることを見据えています。
欧州の動向
欧州でもライセンスの枠組みづくりが進められています。
- 英国のCLA(Copyright Licensing Agency) は、AI訓練専用の「集団ライセンス制度」を創設する計画を進めています。これにより、個々の著者や出版社が直接交渉しなくても、包括的に利用許諾と補償を受けられる仕組みが導入される見通しです。
- フランスのLe Monde は、AI企業との契約で得た収益の25%を記者に直接分配する制度を導入しました。コンテンツを生み出した個々の記者に利益を還元する仕組みは、透明性の高い取り組みとして注目されています。
- ドイツや北欧 でも、出版団体が共同でAI利用に関する方針を策定しようとする動きが出ており、欧州全体での協調が模索されています。
国際的な取り組み
グローバル市場では、出版社とAI企業をつなぐ新たな仲介ビジネスも生まれています。
- ProRata.ai をはじめとするスタートアップは、出版社や著者が自らのコンテンツをAI企業にライセンス提供できる仕組みを提供し、市場形成を加速させています。2025年時点で、この分野は100億ドル規模の市場に成長し、2030年には600億ドル超に達すると予測されています。
- Harvard大学 は、MicrosoftやOpenAIの支援を受けて、著作権切れの書籍約100万冊をAI訓練用データとして公開するプロジェクトを進めており、公共性の高いデータ供給の事例となっています。
出版社の戦略転換
こうした動きを背景に、出版社や報道機関は従来の「読者に販売するモデル」から、「AI企業にデータを提供することで収益を得るモデル」へとビジネスの幅を広げつつあります。同時に、創作者への利益分配や透明性の確保も重視されており、無断利用の時代から「正規ライセンスの時代」へ移行する兆しが見え始めています。
今後の展望
Apple訴訟やAnthropicの巨額和解を経て、AIと著作権を巡る議論は新たな局面に入っています。今後は、法廷闘争に加えて制度整備や業界全体でのルールづくりが進むと予想されます。
1. 権利者側の展望
著者や出版社は引き続き、包括的なライセンス制度と透明性の確保を求めると考えられます。個別の訴訟だけでは限界があるため、米国ではAuthors Guildを中心に、集団的な権利行使の枠組みを整備しようとする動きが強まっています。欧州でも、英国のCLAやフランスの報道機関のように、団体レベルでの交渉や収益分配の仕組みが広がる見通しです。権利者の声は「AIを排除するのではなく、正当な対価を得る」という方向性に収斂しており、協調的な解決策を模索する傾向が鮮明です。
2. AI企業側の展望
AI企業は、これまでのように「フェアユース」を全面に押し出して法廷で争う戦略を維持しつつも、今後は契約と和解によるリスク回避を重視するようになると見られます。Anthropicの早期和解は、その先例として業界に影響を与えています。また、OpenAIやGoogleは政策ロビー活動を通じて、フェアユースの適用範囲を広げる法整備を推進していますが、完全に法的リスクを排除することは難しく、出版社との直接契約が主流になっていく可能性が高いでしょう。
3. 国際的な制度整備
AIと著作権を巡る法的ルールは国や地域によって異なります。米国はフェアユースを基盤とする判例法中心のアプローチを取っていますが、EUはAI法など包括的な規制を進め、利用データの開示義務やAI生成物のラベリングを導入しようとしています。日本や中国もすでにAI学習利用に関する法解釈やガイドラインを整備しており、国際的な規制調和が大きな課題となるでしょう。将来的には、国際的な著作権ライセンス市場が整備され、クロスボーダーでのデータ利用が透明化する可能性もあります。
4. 新しいビジネスモデルの台頭
出版社や報道機関にとっては、AI企業とのライセンス契約が新たな収益源となり得ます。ProRata.aiのような仲介プラットフォームや、新聞社とAI企業の直接契約モデルはその典型です。さらに、著作権切れの古典作品や公共ドメインの資料を体系的に整備し、AI向けに提供する事業も拡大するでしょう。こうした市場が成熟すれば、「正規のデータ流通」が主流となり、海賊版の利用は抑制されていく可能性があります。
5. 利用者・社会への影響
最終的に、この動きはAIの利用者や社会全体にも影響します。ライセンス料の負担はAI企業のコスト構造に反映され、製品やサービス価格に転嫁される可能性があります。一方で、著作権者が適切に補償されることで、健全な創作活動が維持され、AIと人間の双方に利益をもたらすエコシステムが構築されることが期待されます。
まとめ
単なる対立から「共存のためのルール作り」へとシフトしていくと考えられます。権利者が安心して作品を提供し、AI企業が合法的に学習データを確保できる仕組みを整えることが、AI時代における創作と技術革新の両立に不可欠です。Apple訴訟とAnthropic和解は、その転換点を示す出来事だったといえるでしょう。
おわりに
生成AIがもたらす技術的進歩は私たちの利便性や生産性を高め続けています。しかし、その裏側には、以下のような見過ごせない犠牲が存在しています:
- 海賊版の利用 AI訓練の効率を優先し、海賊版が大規模に使用され、権利者に正当な報酬が支払われていない。
- 不当労働の構造 ケニアや南アフリカなどで、低賃金(例:1ドル台/時)でデータラベリングやコンテンツモデレーションに従事させられ、精神的負荷を抱えた労働者の訴えがあります。Mental health issues including PTSD among moderators have been documented 。
- 精神的損傷のリスク 暴力的、性的虐待などの不適切な画像や映像を長期間見続けたことによるPTSDや精神疾患の報告もあります 。
- 電力需要と料金の上昇 AIモデルの増大に伴いデータセンターの電力需要が急増し、電気料金の高騰と地域の電力供給への圧迫が問題になっています 。
- 環境負荷の増大 AI訓練には大量の電力と冷却用の水が使われ、CO₂排出や水資源への影響が深刻化しています。一例として、イギリスで計画されている大規模AIデータセンターは年間約85万トンのCO₂排出が見込まれています 。
私たちは今、「AIのない時代」に戻ることはできません。だからこそ、この先を支える技術が、誰かの犠牲の上になり立つものであってはならないと考えます。以下の5点が必要です:
- 権利者への公正な補償を伴う合法的なデータ利用の推進 海賊版に頼るのではなく、ライセンスによる正規の利用を徹底する。
- 労働環境の改善と精神的ケアの保障 ラベラーやモデレーターなど、その役割に従事する人々への適正な賃金とメンタルヘルス保護の整備。
- エネルギー効率の高いAIインフラの構築 データセンターの電力消費とCO₂排出を抑制する技術導入と、再生エネルギーへの転換。
- 環境負荷を考慮した政策と企業の責任 AI開発に伴う気候・資源負荷を正確に評価し、持続可能な成長を支える仕組み整備。
- 透明性を伴ったデータ提供・利用の文化の構築 利用データや訓練内容の開示、使用目的の明示といった透明な運用を社会的に求める動き。
こうした課題に一つずつ真摯に取り組むことが、技術を未来へつなぐ鍵です。AIは進み、後戻りできないとすれば、私たちは「誰かの犠牲の上に成り立つ技術」ではなく、「誰もが安心できる技術」を目指さなければなりません。
参考文献
本件に直接関係する参考文献
関連で追加調査した参考文献