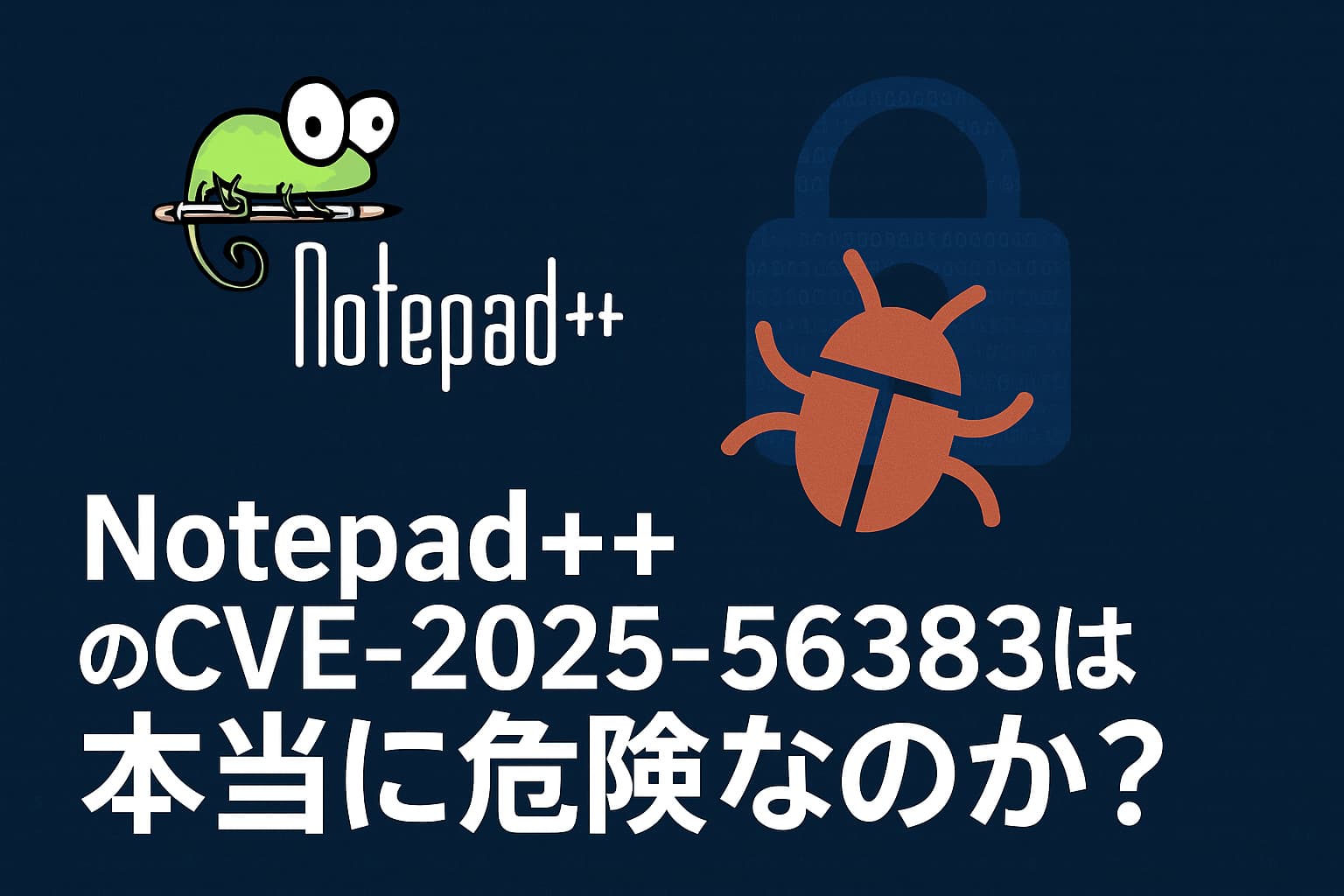はじめに
2025年に入り、テキストエディタ「Notepad++」に関する脆弱性報道がセキュリティ界隈で注目を集めました。特に「CVE-2025-56383」として登録された件は、任意コード実行の可能性が指摘され、一時的に「深刻な脆弱性」として扱われた経緯があります。しかし、報告内容を精査すると、この問題はNotepad++自体の設計上の欠陥というよりも、権限設定や運用環境の問題に起因する限定的なリスクであることが分かります。
本記事では、CVE登録の仕組みや関係機関の役割を整理したうえで、この脆弱性がどのように報告され、なぜ「non-issue(問題ではない)」とされたのかを解説します。さらに、実際に企業や個人がどのような点に注意すべきか、現実的なリスクと対策を冷静に考察します。
目的は「脆弱性が報道された=危険」という短絡的な判断を避け、情報を正しく読み解く視点を持つことにあります。
登場する主な組織と用語の整理
本件(CVE-2025-56383)を理解するためには、いくつかの専門的な名称や組織の関係を把握しておく必要があります。脆弱性は単に「発見された」だけでなく、「誰がそれを登録し」「どのように評価され」「どの機関が公表するか」という複数のプロセスを経て世界に共有されます。
ここでは、登場頻度の高い用語である CVE、NVD、MITRE、NIST、CVA(CVE Numbering Authority) などについて整理し、加えて技術的背景となる DLLハイジャック の基本的な概念にも触れます。これらを理解しておくことで、今回の「Notepad++ の脆弱性報道」がどのような経路で広まり、なぜ「実際には大きな問題ではない」と評価されているのかがより明確になります。
CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)とは
CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)は、世界中で発見・報告されるソフトウェアやハードウェアの脆弱性に一意の識別番号を割り当てるための仕組みです。情報セキュリティ分野で共通言語のような役割を果たしており、「脆弱性を識別・共有するための標準的な枠組み」と言えます。
運営は米国の非営利団体 MITRE Corporation が担い、CVE番号の割り当てを担当する権限を持つ組織を CNA(CVE Numbering Authority) と呼びます。CNAにはMicrosoftやGoogleなどの大手企業、CERT/CC、さらには国家機関などが含まれており、彼らが自社や関連領域で発見された脆弱性に対してCVE-IDを発行します。
CVEに登録される時点では、「この脆弱性が存在するという報告があった」という事実の記録に重点が置かれています。つまり、登録された段階では技術的な真偽や影響度の検証は完了していません。たとえば研究者が脆弱性を報告し、再現性や攻撃シナリオが一定の基準を満たしていれば、ベンダー側がまだ確認中であってもCVE-IDは付与されます。この点が「疑義付きでも登録可能」とされる所以です。
CVE-IDは「CVE-年-番号」という形式で表記されます。たとえば CVE-2025-56383 は、2025年に登録された脆弱性のうち56383番目に付与されたものを意味します。CVEは番号体系を通じて世界中のセキュリティ研究者、製品ベンダー、運用管理者が同じ脆弱性を同一の識別子で参照できるようにするものであり、セキュリティレポート、パッチノート、アラートなどの情報を正確に結びつけるための「基準点」として機能します。
要するにCVEは「脆弱性という事象を世界で一貫して扱うための国際的な識別システム」であり、その信頼性はMITREとCNAの運用体制に支えられています。技術的な深掘りや危険度評価は次の段階である NVD(National Vulnerability Database) に委ねられる点が特徴です。
NVD(National Vulnerability Database)とは
NVD(National Vulnerability Database) は、CVEに登録された脆弱性情報をもとに、技術的な評価や分類を行うための世界標準データベースです。運営しているのは米国の政府機関 NIST(National Institute of Standards and Technology/国立標準技術研究所) であり、政府や企業、研究機関が利用できる公的な脆弱性情報基盤として整備されています。
CVEが「脆弱性の存在を報告したという事実の記録」であるのに対し、NVDはそれを「技術的・客観的に評価し、信頼性を付与する仕組み」です。CVEはあくまで番号付きの“インデックス”に過ぎませんが、NVDはそのCVE-IDに対して次のような詳細データを付加します。
- CVSSスコア(Common Vulnerability Scoring System):脆弱性の深刻度を数値化した評価指標。攻撃の難易度、影響範囲、認証要件などを基準に「Critical/High/Medium/Low」などのレベルで分類します。
- CWE分類(Common Weakness Enumeration):脆弱性の原因や性質を体系的に整理した分類コード。たとえば「CWE-79=クロスサイトスクリプティング」「CWE-427=検索パス制御不備」など。
- 技術的説明・影響範囲・修正状況・参照URL:ベンダーのセキュリティアドバイザリ、CERT報告、GitHub Issueなどを参照して詳細情報を集約します。
- ステータス情報:事実関係に疑義がある場合は “DISPUTED(異議あり)”、誤登録の場合は “REJECTED(無効)” として明示されます。
このようにNVDは、CVEで付けられた識別子に「意味と文脈」を与える役割を担っています。結果として、セキュリティ製品(脆弱性スキャナ、EDR、SIEMなど)や企業の脆弱性管理システムはNVDのデータを直接参照し、リスク評価や優先順位付けを自動的に行います。実際、NVDはJSON形式で機械可読なデータを提供しており、世界中のセキュリティツールの基盤になっています。
重要なのは、NVDがCVEの内容を再検証する立場にあるという点です。CVEの登録があっても、NVDが十分な裏付けを確認できなければ「DISPUTED」として扱い、逆にベンダー公式の修正が確認されればCVSSスコアや技術的解説を更新します。この二段階構造により、CVEの速報性とNVDの信頼性がバランスよく保たれています。
CVEが「脆弱性を世界で一意に識別するための番号」であるのに対し、NVDはその技術的信頼性と危険度を評価するための公的データベースです。NVDが付与するスコアや分類は、企業が脆弱性対策の優先度を判断するうえでの客観的指標として機能しています。
NIST(National Institute of Standards and Technology)とは
NIST(National Institute of Standards and Technology/米国国立標準技術研究所) は、アメリカ合衆国商務省の下に属する国家標準と技術の中核機関です。1901年に設立され、科学・産業・情報技術などの分野における計測基準の策定や標準化の推進を担ってきました。もともとは物理的な「長さ・質量・電圧」といった計測標準を定める機関でしたが、近年ではサイバーセキュリティやデジタル技術の標準化でも国際的なリーダーシップを発揮しています。
サイバーセキュリティ分野におけるNISTの役割は非常に広く、代表的な取り組みには以下のようなものがあります。
- NIST SP(Special Publication)シリーズの策定:情報セキュリティ管理に関するガイドライン群。特に「NIST SP 800」シリーズ(例:SP 800-53、SP 800-171)は、政府機関や民間企業のセキュリティ基準として世界的に参照されています。
- NIST CSF(Cybersecurity Framework):リスク管理の国際標準的枠組み。企業がセキュリティ対策を計画・実行・評価するための基本構造を提供します。
- 暗号技術の標準化:AES(Advanced Encryption Standard)やSHA(Secure Hash Algorithm)など、世界的に使われる暗号アルゴリズムの標準化を主導。
- NVD(National Vulnerability Database)の運営:CVEに登録された脆弱性情報を評価・整理し、技術的な信頼性と危険度を付与する公的データベースを維持しています。
このように、NISTは「標準の策定」と「評価の実装」を両輪として、政府・企業・研究機関の間を橋渡しする存在です。特にNVDのようなデータベース運用では、MITREが付与したCVE-IDを受け取り、それに技術的なメタデータ(CVSSスコア、CWE分類など)を追加する役割を果たしています。
重要なのは、NISTが政府機関でありながら、単なる規制当局ではなく、技術的根拠に基づいて標準を定義する科学的機関だという点です。国家安全保障だけでなく、民間の生産性・信頼性・相互運用性を高めることを目的としており、セキュリティ領域でも「中立的な技術標準」を提供しています。
NISTは「米国の技術標準を科学的根拠に基づいて策定し、世界の産業・IT基盤の信頼性を支える機関」です。その活動の一部としてNVDが運営されており、CVEとMITREを技術的評価の側面から補完しています。
MITREとNISTの関係
MITRE と NIST は、いずれも米国のサイバーセキュリティ体制を支える中心的な組織ですが、その立場と役割は明確に異なります。両者の関係を理解するには、「CVE」と「NVD」という2つの制度がどのように連携しているかを軸に見るのが分かりやすいです。
MITREは非営利の研究開発法人(Federally Funded Research and Development Center, FFRDC) であり、政府から委託を受けて公共システムや国家安全保障関連の研究を行う独立組織です。商用目的で活動する企業ではなく、政府と民間の中間に立って公共利益のための技術基盤を構築することを目的としています。その一環として、MITREは「CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)」の管理主体を務めています。CVEは脆弱性を一意に識別するための国際的な番号体系であり、MITREはその運営を通じて世界中のベンダー、研究者、セキュリティ機関と連携しています。
一方、NIST(National Institute of Standards and Technology)は米国商務省の直轄機関で、国家標準の策定や技術的評価を行う公的機関です。MITREが付与したCVE-IDをもとに、その技術的な詳細、危険度、分類などを分析・整備し、公的データベースとして公開しているのがNISTの運営する NVD(National Vulnerability Database) です。つまり、MITREが「番号を発行する側」、NISTが「その番号に技術的意味づけを与える側」と整理できます。
MITREとNISTの連携は、単なる業務分担ではなく、速報性と信頼性を両立するための二段構造として設計されています。CVEは脆弱性の発見を迅速に記録し、NVDはその内容を技術的に精査して危険度を評価する。この分業により、世界中のセキュリティ関係者が共通の識別子を使いながらも、検証済みで信頼できる情報にアクセスできる仕組みが成り立っています。
また、MITREとNISTは単にCVE/NVDの運営に限らず、脆弱性分類の標準化でも協力しています。たとえば、NVDで使われる CWE(Common Weakness Enumeration) や CAPEC(Common Attack Pattern Enumeration and Classification) といった脆弱性・攻撃手法の体系化プロジェクトはMITREが開発し、NISTがその標準化・適用を支援しています。
MITREは「脆弱性を記録・分類する仕組みを設計する側」、NISTは「その仕組みを国家標準として維持・評価・普及する側」という関係にあります。MITREが“脆弱性情報の発信点”、NISTが“信頼性の担保と制度的基盤”を担うことで、両者は補完的に機能しており、この協力関係こそがCVE/NVDシステムを世界標準たらしめている理由です。
CVA(CVE Numbering Authority)とは
CVA(CVE Numbering Authority) は、CVE識別子(CVE-ID)を正式に発行できる権限を持つ組織を指します。CVEはMITREが運営する仕組みですが、世界中のすべての脆弱性報告をMITREだけで処理するのは現実的ではありません。そのためMITREは、信頼できる企業・団体・政府機関などに「CVA(以前の呼称ではCNA)」としての認定を行い、CVE-IDの発行を分散化しています。
CVAは自らの担当範囲(スコープ)を持っており、その範囲内で発見・報告された脆弱性に対してCVE-IDを割り当てます。たとえば、MicrosoftやGoogleなどは自社製品に関する脆弱性を、Red HatやCanonicalはLinuxディストリビューション関連の脆弱性を、そしてCERT/CCは特定ベンダーに属さない一般的なソフトウェアの脆弱性を担当します。このように、CVA制度は脆弱性管理をグローバルな共同作業体制として運用するための仕組みになっています。
CVAが発行するCVE-IDは、単なる番号の付与にとどまりません。各CVAは報告の内容を確認し、再現性や影響範囲の妥当性を一定の基準でチェックしたうえで登録します。つまり、CVAは「CVEの登録ゲートキーパー」として、最低限の品質を確保する役割を担っています。そのうえで、登録されたCVEはMITREの中央データベースに統合され、後にNISTのNVDで技術的な評価が行われます。
現在では、CVAとして認定されている組織は数百にのぼり、国際的な企業だけでなく政府系CERTや大学研究機関も含まれています。これにより、脆弱性の報告・登録が地域的・業界的に分散され、迅速かつ網羅的な情報共有が実現しています。
CVAは、CVEシステム全体を支える「分散的な信頼のネットワーク」の中心に位置する存在です。MITREが制度を設計し、NISTが評価を担う一方で、CVAは現場レベルで脆弱性情報を最初に拾い上げる現実的な役割を果たしています。
DLLハイジャックとは何か
DLLハイジャックは、Windowsのライブラリ検索順やロード挙動の隙を突き、正規アプリに不正なDLLを読み込ませて任意コードを実行する攻撃手法です。
概念的には次のように動作します。WindowsはDLLをロードする際に複数の場所を順に探します(アプリ実行ファイルのフォルダ、システムフォルダ、Windowsフォルダ、カレントディレクトリ、環境変数PATH など)。この「検索順」を利用し、攻撃者がアプリが先に参照する場所に悪意あるDLLを置くと、アプリは本来の正規DLLではなく攻撃者のDLLをロードして実行してしまいます。これが典型的な「検索パスによるハイジャック」です。類似の手口に「DLLサイドローディング」があり、正規の実行ファイル(ローダー)が設計上把握している任意のDLL名を悪用して、同じフォルダに置いた偽DLLを読み込ませるものがあります。
成立に必要な前提条件は主に二つです。1) ターゲットのプロセスが相対パスや環境依存の検索順でDLLをロードする実装であること。2) 攻撃者がその検索パス上に書き込み可能であること(あるいはユーザ操作で不正ファイルを所定の場所に置かせること)。したがって、管理者権限で「Program Files」へ適切に配置・権限設定されている通常の環境では成功しにくい性質がありますが、ポータブルインストール、誤設定、共有フォルダ、ダウンロードフォルダ経由の実行、あるいは既に端末が侵害されている場合には有効となります。
被害の典型は任意コード実行です。読み込まれたDLLは読み込んだプロセスの権限で動くため、ユーザ権限での永続化、情報窃取、ランサムウェアや後続ペイロードのドロップ、横展開の足掛かりに使われ得ます。サービスや高権限プロセスが対象になれば被害はより深刻になります。
対策はプリンシプルに基づき多層で行います。開発側では明示的なフルパス指定でDLLをロードする、LoadLibraryEx の LOAD_LIBRARY_SEARCH_* フラグや SetDefaultDllDirectories を用いて検索範囲を制限する、署名済みDLLのみを使用する実装にすることが有効です。運用側ではソフトを管理者権限で %ProgramFiles% 配下に配置し一般ユーザーに書き込みを許さない、フォルダACLを厳格化する、WDAC/AppLocker で不正なモジュールの実行を防ぐ、EDRでDLLロードや不審なファイル書き込みを検出・阻止する、といった策を組み合わせます。
検出と監視の観点では、Sysmon の ImageLoaded イベント(Event ID 7)やファイル作成の監査、プロセスツリーの不整合検出、EDRの振る舞い検知ルールを使って不正DLLのロードやインストール時の異常を監視します。加えて定期的なファイル整合性チェックや署名検証を行うと早期発見につながります。
実務的な優先順は、まず「インストール先の権限と配置を統制」すること、次に「実行時のDLL検索挙動を安全化」すること、最後に「検出監視とブロッキング(EDR/WDAC/AppLocker)」でカバーすることです。これらを組み合わせればDLLハイジャックのリスクは実務上十分に低減できますが、開発・運用の両面での作業が必要になります。
CVE-2025-56383とは何か:Notepad++「脆弱性」報道の真相
2025年秋、テキストエディタ「Notepad++」に関する新たな脆弱性として CVE-2025-56383 が登録され、一部のメディアやSNSで「任意コード実行の危険がある」と報じられました。Notepad++ は世界的に利用者が多いOSS(オープンソースソフトウェア)であり、脆弱性の話題は開発者や企業にとって無視できないものです。しかし、この件については早い段階から開発チームが「non-issue(問題ではない)」と明言し、実際に深刻な脆弱性とは見なされていません。
では、なぜこのような「脆弱性報道」が発生し、なぜ公式はそれを否定したのか。ここではCVE-2025-56383の登録経緯、報告内容、公式の見解、そして現実的なリスクを整理し、この問題が実際にはどの程度の重要性を持つのかを見ていきます。
報告内容:Notepad++でのDLLハイジャックの可能性
報告は、Notepad++ のプラグイン DLL を同名の悪意ある DLL に置き換えてロードさせる、いわゆる DLL ハイジャックの可能性を示すものです。PoC は Notepad++ が起動時やプラグインロード時に特定名の DLL を検索して読み込む挙動を利用し、攻撃者がアプリケーションフォルダやカレントディレクトリ、共有フォルダ、ポータブルインストール先など、対象が先に参照する場所に悪性 DLL を配置することで正規 DLL ではなく悪性 DLL を読み込ませる手順を提示しています。読み込まれた DLL は読み込んだプロセスの権限で実行されるため、任意コード実行につながります。
この手口が成功するための前提条件は明確です。第一に Notepad++ が相対パスや検索パスに依存して DLL をロードする実装であること。第二に 攻撃者または非特権ユーザーがその検索パス上にファイルを書き込めること。第三に 標準的な権限分離や配置ポリシー(例えば管理者権限で %ProgramFiles% にインストールし一般ユーザーに書き込み権を与えない)が守られていない環境であること、の三点が満たされる必要があります。これらが満たされない通常のエンタープライズ環境では PoC は成立しにくい性質があります。
想定される攻撃対象はプラグイン DLL(例:plugins\NppExport\NppExport.dll)やアプリがロードする任意のモジュールで、プラグイン経由の持続化や再起動後の永続化が可能になる点が懸念されます。一方で、管理者権限でインストール先を書き換え可能な環境であれば、攻撃者は.exe 本体を差し替えるなど同等あるいは容易な手段を選択できるため、この問題はアプリ固有の欠陥というよりも権限管理や配置ポリシーの不備に起因する側面が大きいです。
実務的な対策としては、インストール先の権限統制、フォルダ ACL の厳格化、WDAC/AppLocker による実行制御、EDR による不正モジュールの検出などを組み合わせることが有効です。
脆弱性として登録された経緯
研究者または報告者が Notepad++ の DLL ロード挙動を利用する PoC を公開または開示しました。その報告は再現手順や PoC を伴っており、CVE 発行の申請基準を満たす形で MITRE(あるいは該当するCVA)に提出されました。
MITRE/CVA 側は提出内容を受けて一意の識別子 CVE-2025-56383 を割り当てました。CVE は「報告が存在する」ことを記録するための識別子であり、この段階で技術的真偽の最終判断は行われません。
その後、NIST が運営する NVD が当該 CVE を受領し、公開データベース上で技術的評価と追加情報の整理を開始しました。並行して Notepad++ 開発チームは GitHub や公式アナウンスで報告内容に反論し、「標準的なインストール環境では成立しにくい」として該当を non-issue と主張しました。
結果として NVD 上では該当案件に disputed(異議あり) の扱いが付され、公式の反論や実運用上の前提条件を踏まえた追加検証が求められる状態になっています。運用者は CVE 自体の存在をトリガーにしつつ、NVD の評価とベンダー公式情報を照合して対応方針を決めるべきです。
Notepad++公式の見解と反論
Notepad++ 開発チームは当該報告について「non-issue(問題ではない)」と明確に反論しています。公式の主張は、PoC が成立するのは「インストール先や検索パスに非特権ユーザーが書き込み可能である」などの前提がある場合に限られ、標準的な管理者権限で %ProgramFiles% 配下に設置され、適切なACLが維持された環境では問題とならない、というものです。開発側は同等の環境であれば実行ファイル(.exe)自体を差し替えた方が容易であり、今回示された手法はアプリ固有の欠陥というよりも権限管理や配置ポリシーの不備を突いた例に過ぎないと説明しています。
技術的な反論点は主に二点です。第一は「検索パス依存のロードが常に存在するとは限らない」という点で、開発側は安全なDLL検索設定やフルパス指定などで回避可能な実装上の措置が取られている旨を指摘しています。第二は「PoC は主にポータブル版やユーザーディレクトリにインストールされたケースで再現されている」点であり、組織で統制された配布手順を採っている環境ではリスクが限定的であるとしています。これらを根拠に、公式は事象の「文脈」を重視して評価すべきと主張しています。
運用上の結論としては、公式の反論を踏まえつつも放置は避けるべきです。公式の指摘どおり標準的なインストールと適切な権限管理を徹底すれば実効的な防止が可能です。並行して、該当報告の詳細やベンダーのアナウンス、NVDのステータス更新を継続して監視し、必要であればインベントリ確認とフォルダACLの是正、EDR/AppLocker/WDACによる補強策を実施してください。
実際のリスクと運用上のポイント
今回のCVE-2025-56383は、報告自体が大きく取り上げられたものの、実際のリスクは環境に強く依存します。リスクの根幹はNotepad++というアプリケーションそのものではなく、権限設定と配置の不備にあります。標準的な管理者権限で %ProgramFiles% 配下にインストールされ、一般ユーザーに書き込み権限がない状態であれば、PoCで示されたDLLハイジャックは成立しません。逆に、ユーザープロファイル下や共有ディレクトリ、ポータブル版の利用など、書き込み可能な環境では不正DLLを置き換えられる可能性が生じます。
したがって運用上の優先課題は「どこに」「どの権限で」Notepad++が存在しているかを把握することです。企業内で使用されている端末を棚卸しし、インストール場所、バージョン、フォルダのアクセス制御リスト(ACL)を確認してください。特に %AppData% やデスクトップ、共有フォルダなどに配置されたポータブル実行ファイルはリスクが高いため、管理対象に含めるべきです。あわせて、公式が修正を反映した最新バージョンへの更新も基本的な対策として実施してください。
権限統制に加え、実行制御と監視も併用することで防御を強化できます。AppLockerやWDACを活用して署名済みの正規DLL以外を実行不可とし、未知のDLLのロードを抑止します。EDR(Endpoint Detection and Response)を導入している場合は、DLLのロード挙動やプロセスツリーの不整合、不審なファイル書き込みを検出できるように設定を見直してください。Sysmonのログ監査やファイル整合性チェックを組み合わせれば、不正DLLの早期発見が可能です。
また、開発者などが例外的にポータブル版を使用する必要がある場合は、申請制とし、限定的なネットワークや検証用環境に閉じ込めて運用するなど、ルール化された例外管理が求められます。ユーザーが自由にインストールできる状況は、今回のような報告を現実的リスクに変える最も大きな要因です。
この脆弱性の性質は「ソフトウェアの欠陥」ではなく「運用設計の不備」が引き金になるものです。NVDでも“disputed(異議あり)”とされているとおり、通常の運用下では深刻な脆弱性とはみなされません。しかし、実際の環境での誤設定は少なくなく、軽視せずに確認・是正・監視を徹底することが安全なシステム運用につながります。
おわりに
CVE-2025-56383 は、表面的には「Notepad++ に任意コード実行の脆弱性がある」として注目されましたが、実際には環境依存のDLLハイジャックの可能性を指摘した報告に過ぎません。標準的なインストール手順と権限設定が守られている環境では成立しにくく、開発チームの見解どおり「non-issue」と位置づけられるのが妥当です。
今回の事例が示したのは、CVEの存在そのものが即「危険」を意味するわけではないということです。CVEはあくまで報告の記録であり、実際のリスク判断にはNVDの評価、ベンダーの公式見解、そして自組織の運用状況を総合的に考慮する必要があります。脆弱性情報を正確に読み解く力こそが、過剰反応と軽視のどちらも避ける最良の防御策です。
結局のところ、重要なのはアプリケーションを正しく配置し、権限管理と更新を怠らない基本的な運用です。セキュリティは特別な対策よりも、日常の管理精度に支えられています。CVE-2025-56383の一件は、その原則を改めて確認する好例と言えるでしょう。
参考文献
- CVE-2025-56383 Detail | National Vulnerability Database
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-56383 - v8.8.6 release: Clarifying the CVE-2025-56383 Non-Issue | Notepad++
https://notepad-plus-plus.org/news/v886-released/ - Notepad++ DLL Hijacking (CVE-2025-56383): CVSS 8.4 or CVSS 0.0? | Trustwave SpiderLabs Blog
https://www.trustwave.com/en-us/resources/blogs/spiderlabs-blog/notepad-dll-hijacking-cve-2025-56383-cvss-8-4-or-cvss-0-0/ - Notepad++ DLL Hijack Flaw Lets Attackers Run Malicious Code on Systems | GBHackers on Security
https://gbhackers.com/notepad-dll-hijack-flaw/ - CVE-2025-56383 – Notepad++ v8.8.3 DLL Hijacking Vulnerability – CVE Details
https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2025-56383/