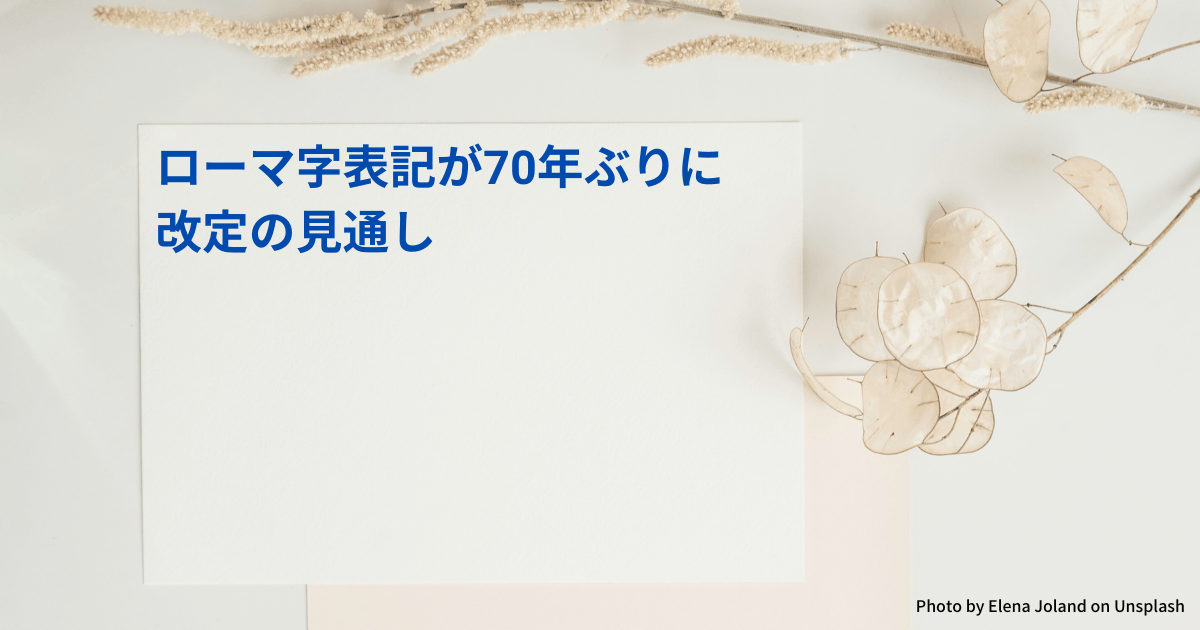学校教育では訓令式ローマ字表記で教えていますが、社会に出てみるとヘボン式ローマ字で書かれている場合がほとんどです。文化審議会国語分科会の国語課題小委員会によると、実態とそぐわない状況を受けて、改定することも視野に入れて検討を進めているそうです。
ヘボン式ローマ字とは
ヘボン式ローマ字(ヘボンしきローマじ)は、日本語の音をローマ字(ラテン文字)で表記する方法の一つです。この方式は、19世紀にアメリカ合衆国の宣教師であるジェームス・カーティス・ヘボン(James Curtis Hepburn)によって考案されました。ヘボン式は、日本語の発音を英語の読み方に近い形で表記することを特徴としています。
ヘボン式ローマ字の特徴は以下のとおりです。
- 母音の表記:「あ」は「a」、「い」は「i」、「う」は「u」、「え」は「e」、「お」は「o」と表記します。
- 子音の表記:基本的に日本語の子音は、英語の発音に近い形でローマ字に変換されます。例えば、「か」は「ka」、「さ」は「sa」、「た」は「ta」、「ふ」は「fu」などとなります。
- 撥音(「ん」):「ん」は、単独で「n」と表記されますが、次に続く音が「b」、「m」、「p」の場合は「m」と表記されることがあります(例:「さんぽ」→「sanpo」)。
- 長音:長い母音は、基本的に母音を重ねて表記します(例:「おおきい」→「ookii」)。
- 促音(小さい「っ」):促音は、次に続く子音を重ねて表記します(例:「きっぷ」→「kippu」)。
訓令式ローマ字とは
訓令式ローマ字(くんれいしきローマじ)は、日本語の音をローマ字(ラテン文字)で表記する方法の一つです。この方式は、日本政府が1946年に公式に採用したもので、ヘボン式ローマ字とは異なる特徴を持っています。
訓令式ローマ字の特徴は以下のとおりです。
- 母音の表記:「あ」は「a」、「い」は「i」、「う」は「u」、「え」は「e」、「お」は「o」と表記します。
- 子音の表記:一部の子音についてはヘボン式と異なり、より日本語の発音に近い形で表記されます。例えば、「し」は「si」、「ち」は「ti」、「つ」は「tu」、「ふ」は「hu」となります。
- 撥音(「ん」):「ん」は常に「n」として表記されます。
- 長音:長い母音は、アクセント記号を付けて表記します(例:「おおきい」→「ôkii」)。
- 促音(小さい「っ」):促音は、次に続く子音を重ねて表記します(例:「きっぷ」→「kippu」)。
業務上はヘボン式ローマ字がメイン
最近だとかなり減ってきた印象ですが、DBのテーブル名、カラム名、プログラムの関数名などで英語に訳せない・訳しにくい場合にローマ字表記を使うことがあります。
その際のルールとして「ヘボン式ローマ字を使用すること」と明文化されているプロジェクトもありますが、そうでないプロジェクトもあります。そのせいか、すでに作成されているテーブルやプログラムを見てみると、ヘボン式と訓令式が混在した書き方になっていることもしばしばです。
これは、訓令式ローマ字に慣れているからではなく、ヘボン式ローマ字に慣れていないことが原因だと考えており、キーボード入力の癖がそのままローマ字に現れているのではないかと思います。
どう改定されるのか
新聞によって書き方は様々ですが、実態に合っていないことが改定の一因になっているため、ヘボン式ローマ字に改定されると予想されています。社会としてはほとんど影響ありませんが、教科書を改定するということになると、生徒や学生、教えている教師の間では混乱が生じるかもしれません。
ヘボン式ローマ字以外の表記方法になるというのはあまり考えにくいですが、どう検討されていくかについては今後も注目していきたいです。